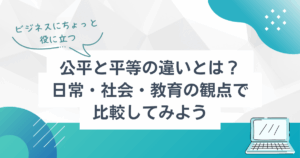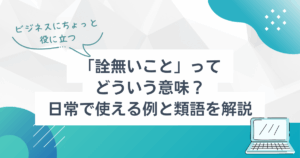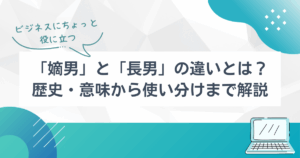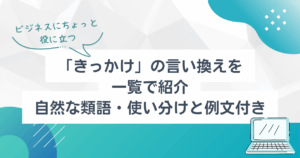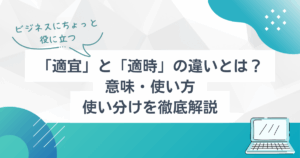家系図の呼び方・見方を一覧でわかりやすく解説【親戚・親族はどう呼ぶ?】

家族や親戚のつながりを視覚的に理解できる「家系図」。しかし、いざ家系図を見ようとすると、「この人は自分から見て何にあたるのか?」「親戚の正しい呼び方がわからない…」と戸惑うことも多いのではないでしょうか。親戚付き合いや相続、冠婚葬祭の場では、正確な呼称を知っておくことが大切です。
そこで本記事では、家系図の基本的な見方や、自分から見た親戚の呼び方を一覧形式でわかりやすく解説します。読み進めることで、家系図がぐっと身近に感じられると思いますので、ぜひご一読ください。
家系図の基本用語と続柄の見方
家系図を理解するためには、「続柄」「直系・傍系」「親等」といった基本用語を正しく把握しておくことが欠かせません。ここでは、これらの用語の意味や違いについてわかりやすくご紹介いたします。
続柄(つづきがら)とは?
「続柄」とは、ある人物から見たときの他の人物との関係性を示す言葉です。たとえば、自分から見て「父」「母」「兄」「妹」などがこれにあたります。
続柄の例
- 父の弟 → 叔父(おじ)
- 母の姉 → 叔母(おば)
- 妹の子 → 姪(めい)または甥(おい)
続柄は戸籍謄本や住民票などの公的書類にも記載されるため、どのような位置づけになるのか正確な理解が求められることもあります。なお、「本人」から見た立場で記述されるのが一般的です。

直系血族・傍系血族とは?
次に、家系図を整理するうえで、「直系」と「傍系(ぼうけい)」の違いも押さえておきましょう。これらは血縁関係を分類する言葉で、次のような違いがあります。
直系血族
自分自身を起点として、親や子、祖父母や孫のように、垂直方向に直接つながる血縁関係を指します。
- 直系尊属: 親、祖父母、曾祖父母など、自分より上の世代。
- 直系卑属: 子、孫、曾孫など、自分より下の世代。
傍系血族
傍系は、自分自身と共通の祖先を持つが、垂直方向に直接つながっていない血縁関係を指します。
具体的には、兄弟姉妹、おじ・おば、いとこ、甥・姪などがこれにあたります。
共通の祖先(例えば、自分と兄弟姉妹であれば両親)を介してつながる関係です。
直系・傍系を覚えるポイントとしては、直系は「上下の関係」、傍系は「横の関係」と考えると良いでしょう。この2つは法律上の相続順位や扶養義務に関係する重要な分類でもあります。
親等(しんとう)はどう数える?
「親等(しんとう)」とは、親族関係の遠近を示す単位です。
自分から見て、どれだけ近い血縁関係にあるかを表しており、この単位は法律や慣習において、相続、扶養義務、婚姻などの場面で重要な役割があります。
直系血族における親等の数え方ルール
直系(自分と直接つながる血縁関係)は、自分から親、子、祖父母、孫のように、世代を1つずつ辿っていくごとに1親等ずつ増えます。
直系血族の親等の数え方例
- 自分から見て、親は1世代上なので1親等
- 自分から見て、祖父母は2世代上なので2親等
- 自分から見て、曾祖父母は3世代上なので3親等
- 自分から見て、子は1世代下なので1親等
- 自分から見て、孫は2世代下なので2親等
傍系血族における親等の数え方ルール
傍系(共通の祖先を持つ血縁関係)は、まず共通の祖先まで世代を遡り、次にその祖先から目的の親族まで世代を下っていくという2段階のプロセスで数えます。
傍系血族の親等の数え方例
- 兄弟姉妹: 自分から親(1親等)に遡り、その親から兄弟姉妹(1親等)に下るので、合計2親等
- おじ・おば: 自分から祖父母(2親等)に遡り、その祖父母からおじ・おば(1親等)に下るので、合計3親等
- いとこ: 自分から祖父母(2親等)に遡り、その祖父母からおじ・おば(1親等)を経由して、いとこ(1親等)に下るので、合計4親等
これらのルールに基づき、血縁関係を明確にすることで、法律上の権利や義務が定められています。
親戚の呼び方を家系図一覧でわかりやすく解説
家系図を見ていても、どの親戚をどう呼べばいいのか迷うことは少なくありません。
特に、親戚付き合いや冠婚葬祭の場面では、正しい呼称を使うことが礼儀とされます。ここでは、家系図でよく使われる親戚の呼び方を、世代別に早見表形式でまとめました。
家系図で使う呼び方一覧表【早見表】

上記を元に、自分(本人)を基準にした呼び方を、上の世代・同世代・下の世代の3つに分けて整理すると次のようになります。
上の世代(尊属)編
| 関係性 | 呼び方 | 説明 |
|---|---|---|
| 父の父 | 祖父 | おじいさんとも呼ぶ |
| 母の母 | 祖母 | おばあさんとも呼ぶ |
| 父または母 | 父・母 | おとうさん、おかあさん |
| 父の兄・弟 | おじ | 年上:伯父、年下:叔父 |
| 母の姉・妹 | おば | 年上:伯母、年下:叔母 |
| 祖父母の兄弟姉妹 | おおおじ・おおおば | 曽祖父母の兄弟姉妹にあたる |
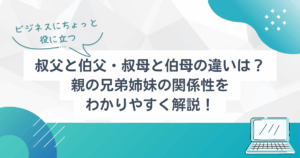
同世代(横のつながり)編
| 関係性 | 呼び方 | 説明 |
|---|---|---|
| 兄弟姉妹 | 兄・弟・姉・妹 | 性別・年齢順で呼称が異なる |
| いとこ | 従兄弟・従姉妹 | 年齢や性別で細かく分かれるが、「いとこ」で通じる |
| 配偶者の兄弟姉妹 | 義兄・義弟・義姉・義妹 | 結婚による姻族関係となる |
「いとこ」は父母の兄弟姉妹の子ども同士の関係です。呼び方は「従兄(じゅうけい)」「従妹(じゅうまい)」などと表現する場合もあります。
下の世代(卑属)編
| 関係性 | 呼び方 | 説明 |
|---|---|---|
| 自分の子 | 息子・娘 | ー |
| 孫 | 孫 | 息子・娘の子 |
| 甥・姪 | 甥・姪 | 兄弟姉妹の子 |
| いとこの子 | 従甥・従姪 | 一般的には「はとこ」とも呼ばれる |
いとこの子については、馴染みがあまりないかもしれませんが、性格には「従甥(じゅうせい)」や「従姪(じゅうてつ)」と呼ばれます。
漢字・読み方・関係性をまとめた呼び方表
親戚の呼び方には、正式な漢字表記と読み方があり、それぞれの関係性を正しく知ることは、特にフォーマルな場面で重要です。ここでは、呼び方の「漢字・読み方・関係性」を一覧で整理し、日常会話との違いや、冠婚葬祭での使い分けについても解説します。
| 漢字 | 読み方 | 関係性 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 父 | ちち | 自分の父 | 「お父さん」とも呼ぶ |
| 母 | はは | 自分の母 | 「お母さん」とも呼ぶ |
| 兄 | あに | 年上の兄弟 | 「おにいさん」とも呼ぶ |
| 弟 | おとうと | 年下の兄弟 | ー |
| 姉 | あね | 年上の姉妹 | 「おねえさん」とも呼ぶ |
| 妹 | いもうと | 年下の姉妹 | ー |
| 伯父 | おじ | 父母の年上の兄弟 | 一般的には「おじさん」 |
| 叔父 | おじ | 父母の年下の兄弟 | |
| 伯母 | おば | 父母の年上の姉妹 | 一般的には「おばさん」 |
| 叔母 | おば | 父母の年下の姉妹 | |
| 従兄弟 | いとこ | いとこ(男性) | 漢字で 「従兄」「従弟」とも表記 |
| 従姉妹 | いとこ | いとこ(女性) | 漢字で 「従姉」「従妹」とも表記 |
| 甥 | おい | 兄弟姉妹の息子 | ー |
| 姪 | めい | 兄弟姉妹の娘 | ー |
なお、表記や呼び方は場面や地域によっても異なる場合がありますので、ご参考として取り扱いください。
正式名称と日常の呼び方の違い
正式な呼称は公的な文書や改まった場面で使われる一方、日常生活ではやや柔らかい言い方が一般的です。
- 「伯父・叔父」→ 「おじさん」
- 「伯母・叔母」→ 「おばさん」
- 「従兄弟・従姉妹」→ 「いとこ」
- 「父・母」→ 「お父さん・お母さん」
やり取りのシーンや相手との関係性によって使い分けることが礼儀になります。ビジネスやフォーマルな文脈では、正式名称を使う方が望ましいでしょう。
冠婚葬祭で使う呼称は?
冠婚葬祭(特に結婚式、葬儀、法事など)で用いられる主な親族の呼称について、一般的なものを表にまとめてご紹介いたします。これらの呼称は、儀式の場で敬意を示すために使われることが多く、普段の会話とは異なる場合がありますので、注意しておきましょう。
上の世代(尊属)に対する呼称
| 続柄 | 一般的な呼称 | 冠婚葬祭での呼称(例) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 父 | お父さん | ご尊父(ごそんぷ)、父 | 弔辞や手紙などで故人を指す場合。 |
| 母 | お母さん | ご母堂(ごぼどう)、母 | 弔辞や手紙などで故人を指す場合。 |
| 祖父 | おじいさん | 祖父、おじいさま | 自分の祖父を指す場合。 |
| 祖母 | おばあさん | 祖母、おばあさま | 自分の祖母を指す場合。 |
| 夫の父 | お義父さん | 岳父(がくふ) | 相手への敬意を示す場合。 |
| 夫の母 | お義母さん | 姑(しゅうとめ) | ー |
| 妻の父 | お義父さん | 岳父(がくふ) | 相手への敬意を示す場合。 |
| 妻の母 | お義母さん | 姑(しゅうとめ) | ー |
| 伯父・叔父 | おじさん | 伯父・叔父、おじさま | 相手への敬意を示す場合。 |
| 伯母・叔母 | おばさん | 伯母・叔母、おばさま | 相手への敬意を示す場合。 |
同世代(横のつながり)に対する呼称
| 続柄 | 一般的な呼称 | 冠婚葬祭での呼称(例) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 旦那さん | 夫、主人 | 場面に応じて使い分け。 |
| 妻 | 奥さん | 妻、家内 | 場面に応じて使い分け。 |
| 兄 | お兄さん | 兄、兄上 | ー |
| 姉 | お姉さん | 姉、姉上 | |
| 弟 | 弟 | 弟 | |
| 妹 | 妹 | 妹 | |
| 兄の妻 | お義姉さん | 義姉、兄嫁(あによめ) | |
| 弟の妻 | お義妹さん | 義妹、弟嫁(おとよめ) | |
| 夫の兄 | お義兄さん | 義兄、兄上 | |
| 夫の弟 | お義弟さん | 義弟、弟上 | |
| 夫の姉 | お義姉さん | 義姉、姉上 | |
| 夫の妹 | お義妹さん | 義妹、妹上 |
下の世代(卑属)に対する呼称
| 続柄 | 一般的な呼称 | 冠婚葬祭での呼称(例) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 子 | 息子・娘 | 子、子息(しそく)・令嬢(れいじょう) | 相手の子を指す場合。 |
| 孫 | 孫 | 孫、孫息(まごそく) | |
| 甥・姪 | 甥っ子・姪っ子 | 甥(おい)・姪(めい) |
続柄の一覧【親等・血族・関係性】
「続柄(つづきがら)」は、家系図や住民票などで自分との関係を表す際に使われる重要な用語です。
しかし、一見すると似たような呼称が並んでいて混乱しやすいのも事実。ここでは、続柄の主な種類とその関係性を一覧形式で整理し、それぞれの意味をわかりやすく解説します。
| 続柄 | 親等 | 血族 | 意味と関係性 |
|---|---|---|---|
| 本人 | 0親等 | 直系 | 基準となる自分自身。 |
| 父・母 | 1親等 | 直系 | 自分を直接産んでくれた両親。 |
| 子 | 1親等 | 直系 | 自分の子ども。 |
| 祖父母 | 2親等 | 直系 | 父母の両親。 |
| 孫 | 2親等 | 直系 | 自分の子の子ども。 |
| 兄弟姉妹 | 2親等 | 傍系 | 父母を同じくする兄弟姉妹。 |
| 曾祖父母 | 3親等 | 直系 | 祖父母の両親。 |
| 曾孫 | 3親等 | 直系 | 自分の孫の子ども。 |
| 伯父・叔父 | 3親等 | 傍系 | 父母の兄弟。 |
| 伯母・叔母 | 3親等 | 傍系 | 父母の姉妹。 |
| 甥・姪 | 3親等 | 傍系 | 自分の兄弟姉妹の子ども。 |
| 高祖父母 | 4親等 | 直系 | 曾祖父母の両親。 |
| 玄孫 | 4親等 | 直系 | 自分の曾孫の子ども。 |
| いとこ | 4親等 | 傍系 | 父母の兄弟姉妹の子ども。 |
| 大伯父・大叔父 | 4親等 | 傍系 | 祖父母の兄弟。 |
| 大伯母・大叔母 | 4親等 | 傍系 | 祖父母の姉妹。 |
| 来孫 | 5親等 | 直系 | 自分の玄孫の子ども。 |
| 高祖父母の 父母 (五世の祖) | 5親等 | 直系 | 高祖父母の父母。 |
| 昆孫 | 6親等 | 直系 | 自分の来孫の子ども。 |
| 高祖父母の 祖父母 (六世の祖) | 6親等 | 直系 | 高祖父母の祖父母。 |
| 再従兄弟・再従姉妹 (またいとこ) | 6親等 | 傍系 | いとこの子ども。 |
義理の関係(姻族)の呼び方にも注意
義理の親族(姻族)に関しても、正式な呼称と日常会話での呼び方が異なります。以下の表で主な姻族関係を確認しておきましょう。
| 関係性 | 正式な呼び方 | 日常的な呼び方 |
|---|---|---|
| 妻の父 | 義父(ぎふ) | お義父さん(おとうさん) |
| 夫の母 | 義母(ぎぼ) | お義母さん(おかあさん) |
| 妻の兄 | 義兄(ぎけい) | お義兄さん (おにいさん・名前にさん付け) |
| 夫の弟 | 義弟(ぎてい) | 名前にくん・さんを付ける |
| 夫の姉 | 義姉(ぎし) | お義姉さん (おねえさん・名前にさん付け) |
| 妻の妹 | 義妹(ぎまい) | 名前にちゃん・さんを付ける |
「義〜」という言葉は、姻族であることを示すために用いられます。ただし「義(ぎ)」を付けた呼び方は日常的には用いられませんので、注意しましょう。
【詳細】上の代(尊属)の呼び方一覧
家系図をたどるうえで、特に「尊属」と呼ばれる自分より上の世代の親族を正しく理解することは、相続や冠婚葬祭の場面でも重要です。
ここではより詳細に、父母・祖父母・曾祖父母といった基本的な呼称だけでなく、親の兄弟姉妹にあたる「伯父・叔父・伯母・叔母」まで整理してご紹介します。
父母・祖父母・曽祖父母・高祖父母・高祖父母の父母・高祖父母の祖父母
自分を基準にして、上の代を6つ遡った尊属の呼び方を世代別にまとめると以下のようになります。
| 関係性 | 世代数 | 親等 | 呼び方 | 読み方 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 親 | 1世代上 | 1親等 | 父 母 | ちち はは | 自分を産んでくれた両親。 |
| 祖父母 | 2世代上 | 2親等 | 祖父 祖母 | そふ そぼ | 両親の両親。 |
| 曾祖父母 | 3世代上 | 3親等 | 曾祖父 曾祖母 | そうそふ そうそぼ | 祖父母の両親。 |
| 高祖父母 | 4世代上 | 4親等 | 高祖父 高祖母 | こうそふ こうそぼ | 曾祖父母の両親。 |
| 高祖父母の 父母 | 5世代上 | 5親等 | 高祖父母の父母 五世の祖 | こうそうそふ こうそうそぼ ごせいのそ | 高祖父母のさらに上の世代の親。 |
| 高祖父母の 祖父母 | 6世代上 | 6親等 | 高祖父母の祖父母 六世の祖 | こうそうそふのそふ こうそうそふのそぼ ろくせいのそ | 高祖父母の上の世代の祖父母。 |
「曾祖父」と「高祖父」の違い
家系図をさらにさかのぼると、「高祖父」「来孫」など、日常ではあまり耳にしない呼び方が登場します。中でも混同しやすいのが「曾祖父(そうそふ)」と「高祖父(こうそふ)」の違いです。
| 呼称 | 読み方 | 自分との関係(世代差) | 説明 |
|---|---|---|---|
| 曾祖父 | そうそふ | 3世代前 | 祖父の父 |
| 高祖父 | こうそふ | 4世代前 | 曾祖父の父 |
曾祖父(ひいおじいさん)に対し、高祖父は「ひいひいおじいさん」にあたります。家系図やルーツを調べるときに、代を正確に数えることがポイントです。
「伯父」「叔父」「伯母」「叔母」など親の兄姉・弟妹の呼び方
親の兄弟姉妹の呼び方も、日常会話では「おじさん」「おばさん」で済ませがちですが、正式には以下のように区別されます。
| 続柄 | 呼び方 | 年齢による違い | 解説 |
|---|---|---|---|
| 父・母の兄 | 伯父(はくふ) | 父・母より年上 | 日常ではどちらも 「おじ」を使用 |
| 父・母の弟 | 叔父(しゅくふ) | 父・母より年下 | |
| 父・母の姉 | 伯母(はくぼ) | 父・母より年上 | 日常ではどちらも 「おば」を使用 |
| 父・母の妹 | 叔母(しゅくぼ) | 父・母より年下 |
会話では「おじ」「おば」で通じますが、招待状などで正確な続柄を記載するシーンにおいては「伯父」「叔母」などの表記が必要です。なお、親の兄弟姉妹の配偶者にあたる「義理のおじ・おば」は、「義伯父」「義叔母」などと呼ばれることもあります。
【詳細】同じ世代の親戚の呼び方
同世代の親戚は、日常的な付き合いが多い分、呼び方を正しく理解しておくと人間関係もスムーズになります。
ここでは、自分と同じ世代にあたる兄弟姉妹、いとこ(従兄弟姉妹)、義理の関係にあたる親戚の呼び方について、詳しく解説します。
兄弟姉妹の呼び方(兄・弟・姉・妹)
兄弟姉妹は血縁関係の中でも特に近い存在であり、それぞれの呼び方には年齢と性別が関係します。
| 続柄 | 呼び方 | 条件/意味 |
|---|---|---|
| 兄 | あに | 自分より年上の男性の兄弟 |
| 弟 | おとうと | 自分より年下の男性の兄弟 |
| 姉 | あね | 自分より年上の女性の姉妹 |
| 妹 | いもうと | 自分より年下の女性の姉妹 |
話し言葉では「お兄さん」「お姉さん」などの丁寧表現がよく使われます。対外的には「兄」「姉」などが一般的です。
いとこ/従兄弟姉妹/再従兄弟姉妹(はとこ)など
「いとこ」は、自分の父母の兄弟姉妹の子どもにあたる親戚です。さらに、その子ども同士の関係を「再従兄弟姉妹(はとこ)」と呼びます。
| 続柄 | 漢字 | 読み方 | 説明 |
|---|---|---|---|
| いとこ | 従兄弟 従姉妹 | じゅうけいてい じゅうしまい | 同世代 4親等の傍系血族 |
| はとこ | 再従兄弟 再従姉妹 | さいじゅうけいてい さいじゅうしまい | いとこの 子ども同士の関係 自分とは6親等の傍系血族 |
会話では「いとこ」「はとこ」で通じますが、正式文書や紹介文では漢字表記に注意しましょう。
義理関係での呼び方(義兄・義姉・義父・義母など)
結婚などによって生じる親戚関係を「姻族」と呼びます。この場合、自分と血縁関係のない義理の親戚に対しては、名前の前に「義」を付けて呼びます。
| 続柄 | 呼び方 | 意味・説明 |
|---|---|---|
| 義兄 | ぎけい | 配偶者の兄、自分の姉の夫など |
| 義弟 | ぎてい | 配偶者の弟、自分の妹の夫など |
| 義姉 | ぎし | 配偶者の姉、自分の兄の妻など |
| 義妹 | ぎまい | 配偶者の妹、自分の弟の妻など |
| 義父 | ぎふ | 配偶者の父、 自分の母の再婚相手など |
| 義母 | ぎぼ | 配偶者の母、 自分の父の再婚相手など |
口語では「お義兄(おにい)さん」「お義母(おかあ)さん」などと柔らかく表現されることが多いですが、冠婚葬祭や文書上では正式表現が用いられます。
【詳細】下の代(卑属)の呼び方一覧
「卑属(ひぞく)」とは、自分よりも下の世代にあたる親族のことを指します。家系図では子や孫を中心に、さらにその先の世代まで記載されることもあり、正確な呼称の理解が求められます。ここでは、卑属の主な呼び方を世代別に整理し、一般的な呼称との違いも含めて紹介します。
子・孫・曾孫・玄孫など
直系卑属である自分の子孫については、以下のように世代ごとに呼び方が異なります。
| 続柄 | 呼び方 | 世代差 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 子 | 息子・娘 | 1代下 | 1親等 |
| 孫 | まご | 2代下 | 2親等 |
| 曾孫 | そうそん ひまご | 3代下 | 3親等 |
| 玄孫 | げんそん やしゃご | 4代下 | 4親等 曾孫の子 |
| 来孫 | らいそん | 5代下 | 5親等 玄孫の子 |
| 昆孫 | こんそん | 6代下 | 6親等 来孫の子 |
| 仍孫 | じょうそん | 7代下 | 7親等 昆孫の子 |
日常会話では「ひ孫」「やしゃご」までが一般的ですが、家系研究や戸籍調査では「来孫」「昆孫」まで登場することもあります。
甥・姪・姪孫・又甥・又姪など
兄弟姉妹やいとこの子どもたちにあたる「傍系卑属」も、正確な呼称が存在します。
| 続柄 | 呼び方 | 関係性の説明 |
|---|---|---|
| 甥 | おい | 兄弟姉妹の息子 3親等の傍系親族 |
| 姪 | めい | 兄弟姉妹の娘 3親等の傍系親 |
| 姪孫 | てっそん | 甥・姪の子 4親等の傍系親族 |
| 又甥 | またおい | 甥の子で、姪孫と同義 4親等の傍系親族 |
| 又姪 | まためい | 姪の子で、姪孫と同義 4親等の傍系親族 |
「姪孫(てっそん)」は読み方に注意が必要です。日常では「甥の子」「姪の子」で通じる場合が多いですが、正式文書では「姪孫」と表記されることもあります。
いとこの子供・孫など、聞き慣れない呼び方
「いとこの子ども」や「いとこの孫」にあたる関係は、家族的にはやや遠いものの、法的・血縁的には明確な呼称があります。
| 関係性 | 呼び方 | 備考 |
|---|---|---|
| いとこの子 | 従甥・従姪 | 「じゅうせい」 「じゅうてつ」などと読む |
| いとこの孫 | 従姪孫 | 「じゅうてっそん」 |
これらの呼称は、法律や戸籍関係では用いられることがあるようですが、日常的なシーンではあまり使われないと思われます。会話では名前にちゃん・くんを付けることが多いでしょう。
敬語・日常語での呼び方との差
親戚や家族を呼ぶ際には、場面に応じた適切な言葉遣いが求められます。普段使っている「おじいちゃん」「おばさん」などの呼び方と、正式な場での表現には明確な違いがあるため、状況に応じた使い分けが必要です。ここでは、日常語と敬語、冠婚葬祭での表現の違いを具体的に紹介します。
普段の呼び方(おじいちゃん/おばあちゃんなど)
家庭内や親しい間柄で使われる呼び方は、柔らかく親しみのある表現が多く、主に「ちゃん」「さん」などを付けて呼ぶことが一般的です。
| 続柄 | 日常的な呼び方 |
|---|---|
| 祖父 | おじいちゃん |
| 祖母 | おばあちゃん |
| 父 | お父さん |
| 母 | お母さん |
| 伯父・叔父 | おじさん |
| 伯母・叔母 | おばさん |
| 兄 | お兄ちゃん/お兄さん |
| 姉 | お姉ちゃん/お姉さん |
このような呼び方は、親しみを込めた言葉遣いとして一般的です。
正式/礼儀の場で使う名称(祖父・曾祖父・伯父など)
ビジネスシーンや、改まった席では、血縁関係を正確に伝えるために、正式な漢字と敬称を使う必要があります。特に冠婚葬祭やビジネス上の紹介文などでは注意が必要です。
| 日常語 | 正式な表現 | 用途例 |
|---|---|---|
| おじいちゃん | 祖父(そふ) | 挨拶文、席次表など |
| おばあちゃん | 祖母(そぼ) | |
| ひいおじいちゃん | 曾祖父(そうそふ) | 家系図や法的書類 |
| おじさん | 伯父/叔父(はくふ/しゅくふ) | 相手の年齢により使い分け |
| おばさん | 伯母/叔母(はくぼ/しゅくぼ) | |
| お兄さん | 兄(あに) | 「ご尊兄様」などと 表現されることも |
| お姉さん | 姉(あね) | 礼状では「ご令姉様」など |
家系図を見る時・作る時のコツ
家系図は、家族の歴史を可視化するだけでなく、親族関係の理解や相続・冠婚葬祭の際にも役立つ重要な資料です。しかし、実際に見る・作るとなると「誰が誰か分からない」「呼び方が複雑」と感じることも多いはず。ここでは、家系図をより分かりやすく、正確に扱うための工夫を紹介します。
漢字の読み方を付ける・振り仮名を使う
家系図には「伯父」「従甥」「曾祖父」など、普段目にしない漢字も多く登場します。そのため、すべての氏名・続柄にフリガナ(読み仮名)を付けることがとても大切です。
- 親戚の子ども世代や読み間違いを防げる
- 将来的に引き継ぐ人にも優しい
- 手書きでもデジタルでも一目で理解できる
特に読み方に迷いやすい「姪孫(てっそん)」「従兄弟・従姉妹(いとこ・じゅうけいてい・じゅうしまい)」などは、必ず読み仮名を添えておきましょう。
系統(父系・母系)を色分けするなど視覚的工夫も
見やすい家系図を作るうえで、視覚的な整理はとても重要です。特に「父方」「母方」や「義理の親族」といった区別を色や線で表すと、家系全体が格段に理解しやすくなります。
- 父系=青、母系=赤でラインを色分け
- 義理の関係(姻族)には点線を使用
- 故人には背景グレー、存命者には白などで区別
- 名前の下に「生没年」や「出身地」なども補記
Excelや家系図作成ソフトを活用すれば、色分けや図形の整理も簡単に行えます。
続柄が分からない時の調べ方(戸籍・親戚に聞く・ネット辞典など)
古い家系図や親族の話だけでは、正しい続柄がわからないケースもあります。そのような場合には、以下の方法で情報を確認・補完するとよいでしょう。
- 戸籍謄本を見る
正確な続柄と親等が記載されており、公的にも信頼できる情報源です。 - 親戚に聞く
特に年配の親族は家族の歴史をよく知っているため、有力な情報源になります。 - ネットの家系図辞典・続柄一覧を活用する
「〇〇 続柄」で検索すれば、用語の意味や相関図が出てくるサイトが多数あります。 - 図書館で家系図の専門書を調べる
旧家・武家の系図などは、地域史や家系学の資料として図書館に所蔵されていることがあります。
正確な情報が曖昧なままだと、家系図全体に誤解が生まれてしまうこともあるため、可能な限り一次情報にあたることが大切です。
まとめ:家系図を正しく理解することが、親族関係を深める第一歩
家系図は、ただの図表ではなく、家族の歴史やつながりを理解するための大切なツールともいえます。本記事では、以下のようなポイントについて詳しく解説してきました。
- 「続柄」や「親等」などの基本用語と見方
- 親戚の呼び方を世代別に整理した早見表
- 日常語と正式な呼称の使い分け
- 義理の親族(姻族)の正しい呼び方
- 家系図を作る際の視覚的工夫や注意点
これらを理解しておくことで、冠婚葬祭や相続、親族とのコミュニケーションの場でスムーズにやり取りができると思います。
ぜひ今回の内容を参考に、自分だけの家系図を読み解き、あるいは作ってみてはいかがでしょうか。家族や親族への理解が、きっと今まで以上に深まることでしょう。