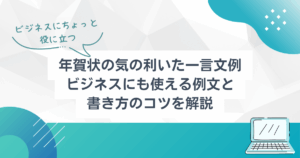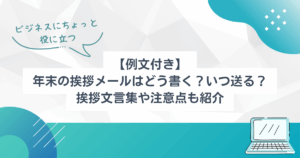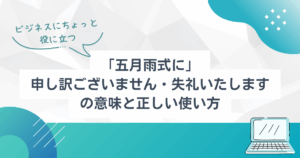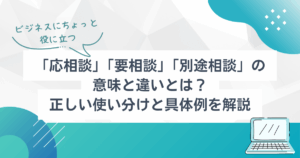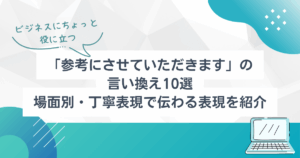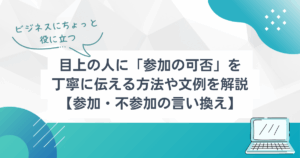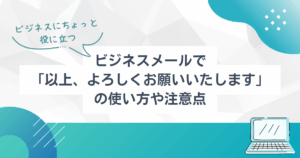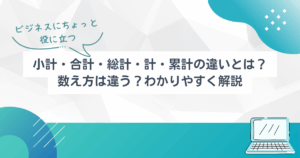叔父と伯父・叔母と伯母の違いは?親の兄弟姉妹の関係性をわかりやすく解説!
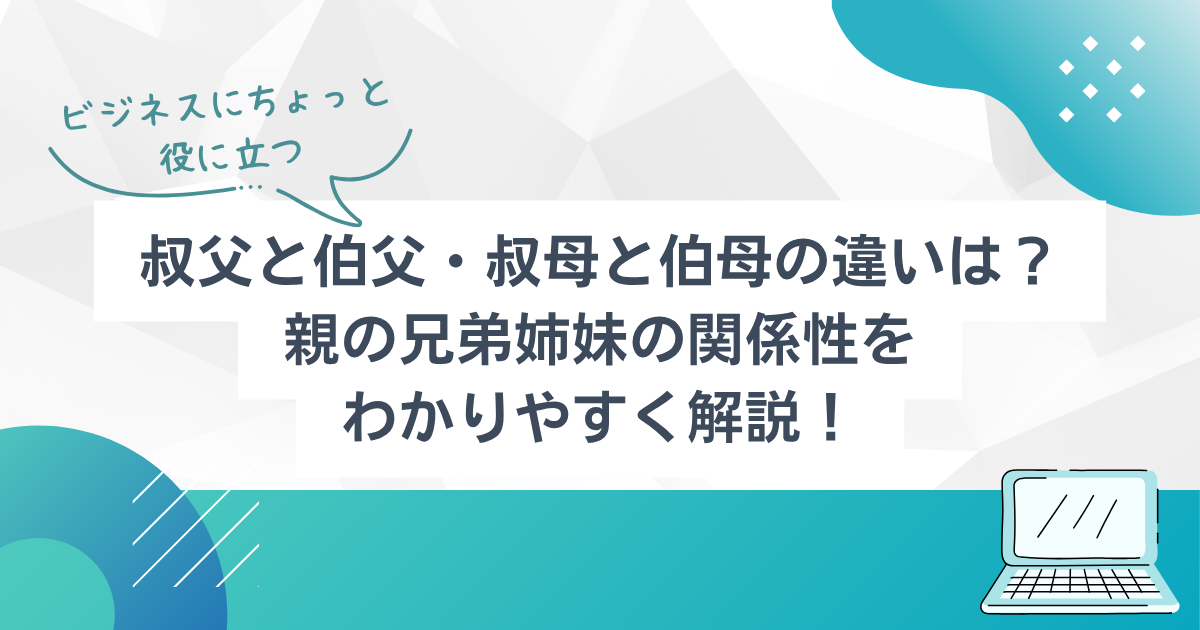
家族を表す日本語には、似ているようで使い分けが難しい言葉がいくつかあります。その代表例が「叔父(おじ)と伯父(おじ)」「叔母(おば)と伯母(おば)」ではないでしょうか。
どちらも親の兄弟姉妹を指す言葉ですが、実は漢字の使い分けに明確なルールがあります。普段の会話においては「おじ」「おば」呼びとなるため漢字の違いはあまり意識されないかもしれませんが、年賀状や正式な文書などでは正しく使い分けたいものです。
今回のコラム記事では、それぞれの意味や違いをわかりやすく解説し、覚えやすいポイントも紹介していきますので、ぜひご一読ください。
まず押さえたい「叔父と伯父「叔母と伯母」に関する基本ルール
「叔父・伯父」「叔母・伯母」の違いを理解するためには、まず共通する読み方と、その使い分けのルールを押さえておくことが大切です。ここを理解すれば、日常生活でも自然に正しい漢字を選べるようになるでしょう。
「おじ」「おば」は同じ読み、漢字で使い分ける
日本語では「おじ」「おば」という言葉自体には漢字がつかないため、漢字表記をする際に「叔父・伯父」「叔母・伯母」と書き分ける必要があります。
つまり、発音は同じでも、文章の中では正しく漢字を当てることで相手に伝わりやすくなるのです。
おじ
叔父 or 伯父
おば
叔母 or 伯母
このように、同じ「おじ」「おば」でも、漢字で表記することよって立場や年齢関係がはっきりと区別されることになります。
使い分けの基準は「親より年上か年下か」
最大のポイントは「親より年上か年下か」という基準です。
整理すると、
- 親より年上の兄や姉 → 「伯父」「伯母」
- 親より年下の弟や妹 → 「叔父」「叔母」
上記のような使い分けとなります。
つまり、漢字の選び方は親との関係性で決まります。単純に「自分にとっておじ・おば」ではなく、「親から見た兄か弟か、姉か妹か」という点を意識すれば迷いにくいでしょう。
例えば、父の兄であれば「伯父」、母の妹であれば「叔母」となります。このように基準を明確に理解しておくことで、公式な文書や日常の手紙でも自信を持って使い分けられるはずです。

叔父と伯父の違いを整理しよう
前述のとおり、「おじ」と一口に言っても実際には親の兄か弟かによって漢字の表記が変わります。この章では「伯父」と「叔父」の違いを整理し、混乱しやすいポイントをクリアにしていきましょう。
伯父とは?(親の兄の場合)
「伯父(おじ)」は、自分の親よりも年上の兄を指します。
- 父の兄
- 母の兄
このように、親より上の立場にある兄弟が「伯父」です。
日常会話では区別しなくても通じますが、年賀状や冠婚葬祭などフォーマルな場面では正しい漢字を用いることが望ましいでしょう。
叔父とは?(親の弟の場合)
一方、「叔父(おじ)」は、自分の親よりも年下の弟を意味します。
- 父の弟
- 母の弟
つまり「伯父」と「叔父」は、親との兄弟関係によって区別されるのです。
親との兄弟関係を基準に考えるとわかりやすい
「おじ」の漢字表記である「伯父(おじ)」と「叔父(おじ)」の使い分けは、「年齢」というより「親との兄弟関係」(親から見てその兄弟が年上か年下か)を基準にするとわかりやすいでしょう。
具体的には、
- 親の兄(年上の兄弟)であれば、常に「伯父」と表記します。
- 親の弟(年下の兄弟)であれば、常に「叔父」となります。
したがって、「おじ」の漢字表記は、親から見てその兄弟が「兄(年上)なのか弟(年下)なのか」という「親との年齢の上下関係」をもとに判断するのが正しいルールといえます。
伯母と叔母の違いを整理しよう
「おば」もまた、「伯母」と「叔母」という二つの表記があり、親との関係性によって使い分けます。音は同じですが、意味合いは明確に異なるため、場面に応じて正しく理解しておくことが重要です。
伯母とは?(親の姉の場合)
「伯母(おば)」は、親より年上の姉を指します。
- 父の姉
- 母の姉
親にとって上の兄弟姉妹という位置づけであり、敬意をもって表現する際にも用いられます。文章では「おばさん」と書くよりも「伯母さん」と漢字を使うことで、より丁寧で正確な表記となります。
叔母とは?(親の妹の場合)
一方、「叔母(おば)」は、親より年下の妹を意味します。
- 父の妹
- 母の妹
「叔母」も「伯母」と同様、親との兄弟関係に基づいて判断します。日常会話では区別せずに「おば」と言うことが多いですが、正式な文章や挨拶状では正確に使い分けることが望ましいでしょう。
年齢や性別で迷わない基準
「伯母」と「叔母」の違いを理解する上で重要なのは、年齢そのものではなく「親との関係性」が基準にするとわかりやすいです。
具体的には、親の姉妹のうち、親より
- 年上(母の姉) → 伯母
- 年下(母の妹) → 叔母
となります。
例えば、親の姉(伯母)であっても年齢的に若々しく見える場合がありますが、それでも「伯母」です。逆に、親の妹(叔母)が年齢的に上に見えても「叔母」となります。
このように、見た目の年齢ではなく、あくまで親から見て姉(年上)なのか妹(年下)なのかという家族関係を基準に考えれば、迷うことはありません。
配偶者・義理の「おじ・おば」の表記
親族関係の表記は、血縁だけでなく「義理の関係」においても正しく区別する必要があります。特に結婚後は、配偶者の兄弟姉妹やその配偶者をどのように呼ぶか迷いやすいため、ここで整理しておきましょう。
義伯父・義叔父・義伯母・義叔母とは
結婚などでつながる「義理の親族」(姻族)を厳密に区別する場合、頭に「義」をつけて表記します。この「義〇〇」という表記は、主に配偶者の伯父・叔父・伯母・叔母を指す際に用いられます。
| 表記 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| 義伯父 | ぎはくふ | 配偶者の親の兄、または自分の叔母の夫など |
| 義叔父 | ぎしゅくふ | 配偶者の親の弟(またはその夫) |
| 義伯母 | ぎはくぼ | 配偶者の親の姉(またはその妻) |
| 義叔母 | ぎしゅくぼ | 配偶者の親の妹(またはその妻) |
ただし、自分の伯父/叔父の妻や、伯母/叔母の夫については、慣習上「義」をつけず「伯母/叔母」「伯父/叔父」と呼ぶのが一般的です。
このように「義〇〇」という表記を用いることで、血縁ではなく婚姻関係によって生じる親族であることを明確に示すことができます。
配偶者側の姉妹・兄弟の使い分け
配偶者の親族についても、基本的なルールは血縁の場合と同じです。つまり、親(義父母)より年上か年下かが基準となります。
- 配偶者の父の兄 → 義伯父
- 配偶者の父の弟 → 義叔父
- 配偶者の母の姉 → 義伯母
- 配偶者の母の妹 → 義叔母
例えば、夫の母の姉であれば「義伯母」、妻の父の弟であれば「義叔父」と表記します。
このように、「義」をつけて整理することで、結婚後の冠婚葬祭や年賀状などの正式な文書においても、正確で丁寧な表現ができるでしょう。
親等・法律上の表現方法や取り扱いについて
「叔父・伯父・叔母・伯母」は、日常的な呼び方だけでなく、法律や戸籍上の取り扱いにも関わってきます。ここでは、親等の数え方や相続・忌引といった具体的な場面での扱いを解説していきます。
叔父・伯父・叔母・伯母は何親等?
民法で定められた「親等」では、親や子を基準にして血縁関係の近さを表します。
- 自分と親 → 1親等
- 自分と祖父母 → 2親等
- 自分と叔父・伯父・叔母・伯母 → 3親等
つまり、「おじ」「おば」にあたる人たちはすべて三親等に分類されます。親より年上か年下かの区別(伯・叔)にかかわらず、親等の上では同じ扱いとなります。
親等の数え方や考え方については、下記コラム記事で詳細を解説していますので、併せてご一読ください。

相続・忌引・戸籍における「伯父・叔父」と「伯母・叔母」の立場
相続、忌引、戸籍という法律や公的な手続きの場において、「伯父・叔父」および「伯母・叔母」という続柄(ぞくがら)が、どのような立場で扱われるのかを解説します。

相続における「伯父・叔父」と「伯母・叔母」
伯父、叔父、伯母、叔母(父母の兄弟姉妹)は、通常、法定相続人にはなりません。
なお、相続の文脈では、「伯父」「叔父」といった年齢の上下を示す漢字は使用されず、法定相続人の範囲としては「(父母の兄弟姉妹)」の立場として扱われます。
忌引における「伯父・叔父」と「伯母・叔母」
忌引休暇の基準は法律で定められているわけではなく、企業や学校の就業規則・学則に委ねられています。しかし、多くの組織が国家公務員の例などに準じており、伯父、叔父、伯母、叔母の忌引日数は全国的に共通した目安があります。
| 続柄 | 忌引日数(目安) | 法律上の表記 |
|---|---|---|
| 伯父・叔父・伯母・叔母 | 1日〜3日 | 特に定められた法律上の表記はないが、「父母の兄弟姉妹」として扱われる。 |
戸籍における「伯父・叔父」と「伯母・叔母」
戸籍謄本などに「伯父・叔父」などの漢字表記が直接記載されることは通常はないかと思われます。あくまで「誰の子(または親、兄弟)である」という形で、他の親族との関係性を通じて把握されます。
戸籍法において、「伯父」「叔父」といった漢字表記を区別して使用することはありません。「傍系血族(ぼうけいけつぞく:共通の祖先を持つが直系の親子関係にはない血族)」であり、本人から見て3親等という事実が重要になります。
混同しやすいケースと注意点
「叔父・伯父」「叔母・伯母」の違いはシンプルですが、実際の生活では混同してしまう場面も少なくありません。ここでは、特に注意したいケースや、誤解を避けるための工夫を紹介します。
実年齢が基準にならない例
もっとも誤解が生じやすいのは「見た目」で判断してしまうケースではないでしょうか。
例えば、父の弟(叔父)が兄(伯父)より年上に見えることもあります。しかし、親にとって兄なら伯父、弟なら叔父という基準は変わりません。
つまり、見た目ではなく、あくまでも「親との続柄」に基づいて表記するのが正しい使い分けです。
父方・母方での誤解を避ける方法
もう一つ間違いやすいのが、「父方のおじ」と「母方のおじ」を混同するケースです。
同じ「伯父」でも、父の兄なのか母の兄なのかを区別しなければ、相手に正確に伝わりません。
そのため、必要に応じて
- 父方の伯父/母方の伯父
- 父方の叔母/母方の叔母
上記のように補足すると誤解が避けられます。特に親族が多い場合や、結婚式など親戚同士が集まる場では「父方」「母方」を明記することが望ましいでしょう。
手紙・席次表などでの正式表記
冠婚葬祭や公式な文書では、必ず正しい漢字を用いる必要があります。
- 年賀状や挨拶状
- 「伯母夫婦に新年のご挨拶を申し上げます」など、正しい表記で書くと丁寧な印象になります。
- 結婚式の席次表
- 「伯母 ○○様」など、肩書きとともに明記することで誤解なく伝わります。
- 香典や弔電
- 「伯父 ○○様 ご逝去の報に接し…」といったように、親族関係を正しく書き分けることが礼儀とされています。
このように、普段は「おじ」「おば」とひらがなで済ませることが多いものの、正式な場面では必ず「伯」「叔」を区別して使うことがマナーと言えるでしょう。
まとめ:「叔父と伯父」と「叔母と伯母」は親を基準に考えよう
「叔父・伯父」「叔母・伯母」の違いは、親より年上か年下かというシンプルな基準で決まります。
- 親の兄・姉 → 伯父・伯母
- 親の弟・妹 → 叔父・叔母
- 義理の関係では「義伯父・義叔父・義伯母・義叔母」と表記
- 親等上はいずれも「三親等」にあたる
日常会話では「おじ」「おば」とひらがなで済ませても問題ありませんが、年賀状・手紙・席次表・戸籍など正式な場面では、正しい漢字を使い分けることが重要です。
この使い分けを押さえておけば、家族関係を正しく表現できるだけでなく、礼儀を重んじた丁寧な印象を与えることができるでしょう。