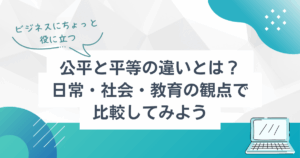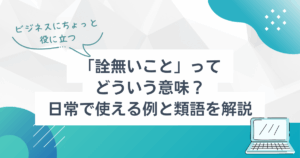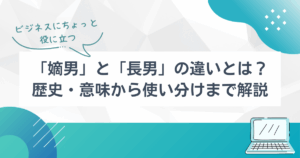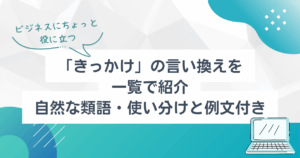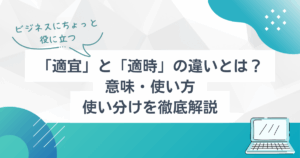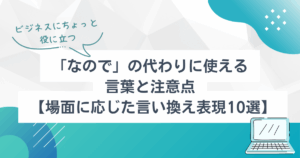12月に使いたい時候の挨拶:上旬・中旬・下旬に分けた季節の言葉と例文集【年末のご挨拶】

1年の締めくくりとなる12月は、寒さが一段と増し、街にも年末らしい慌ただしさが漂う季節です。仕事や私生活の節目にあたるこの時期は、感謝や気遣いの気持ちを込めた時候の挨拶を添えることで、文章に温かみと誠実さを与えることができます。
12月は上旬・中旬・下旬で気候や行事の雰囲気が大きく変わるため、それぞれの時期に合わせた言葉選びが大切です。初冬の凛とした空気を感じる上旬から、年の瀬のあわただしさが増す下旬まで、季節の移ろいを丁寧に表現しましょう。
本記事では、12月の時候の挨拶を上旬・中旬・下旬ごとにわかりやすく解説。ビジネス文書や年賀状、季節のご挨拶メールなどに使える漢語調・口語調の例文をまとめてご紹介します。
12月の時候の挨拶とは?~上旬・中旬・下旬で使い分けよう~
12月は、寒さが一段と厳しくなり、年の瀬のあわただしさが感じられる季節です。木々の葉が落ち、冬の静けさが街に広がる一方で、クリスマスや年末の行事で心が弾む時期でもあります。
この時期の時候の挨拶では、「一年を振り返る感謝」と「新しい年への思い」を自然に込めることが大切です。ビジネスでも私信でも、相手を気遣う温かみのある一文を選びましょう。
12月の季節感と挨拶選びのポイント:冬本番の寒さと年の瀬を伝える時候の挨拶とは
12月の上旬は、初冬の冷たい空気が漂い始め、冬の訪れを実感する頃です。中旬にかけては本格的な寒さが到来し、下旬になると街は年末の雰囲気に包まれます。
時候の挨拶では、
- 上旬は寒さの始まりを意識して:「初冬の候」「大雪の候」
- 中旬は「冬の深まり」下旬は「年の瀬・感謝」を意識して:「寒冷の候」「歳末の候」「年末厳寒の候」
このような表現を選ぶと自然です。
12月の時候の挨拶の選び方のポイント
- 12月上旬(12月1日~12月10日頃)
- 初冬の始まりと寒くなり始めの時期を表現します。二十四節気では「大雪(たいせつ)」に入る頃で、本格的な冬の到来を感じさせる表現を選びます。「師走」は12月全般に使えますが、上旬から使用しても問題ありません。
- 漢語調では:「初冬の候」「大雪の候」「向寒の候」「師走の候」など
- 口語調では:「師走に入り、寒さも日増しに強まってまいりました。」「各地から初雪の便りが届く季節となりました。」など
- 「歳末(さいまつ)」や「冬至(とうじ)」といった年末色が強い言葉は、上旬には避けるのが無難です。
- 初冬の始まりと寒くなり始めの時期を表現します。二十四節気では「大雪(たいせつ)」に入る頃で、本格的な冬の到来を感じさせる表現を選びます。「師走」は12月全般に使えますが、上旬から使用しても問題ありません。
- 12月中旬(12月11日~12月20日頃)
- 寒さが一段と厳しくなり、年末の忙しさ(師走の多忙)が本格化する時期を表現します。日暮れの早さや、イルミネーションなど年末の風物詩に触れるのも良いでしょう。
- 漢語調では:「寒気の候」「短日の候」「厳寒の候」「歳末の候」など
- 口語調では:「冬の寒さが身に染みる頃となりました。」「日一日と寒さがつのってまいりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。」など
- 中旬は「大雪」の時期と重なりますが、下旬に近づくにつれて「歳末」などの年末の表現も取り入れ始めます。「冬至」はまだこの時期には早い表現です。
- 寒さが一段と厳しくなり、年末の忙しさ(師走の多忙)が本格化する時期を表現します。日暮れの早さや、イルミネーションなど年末の風物詩に触れるのも良いでしょう。
- 12月下旬(12月21日~12月31日)
- 一年で最も昼が短い「冬至(とうじ)」を迎え、いよいよ年の瀬を迎える時期です。年末の慌ただしさや、一年間の感謝、新年の挨拶といった要素を含んだ表現が適切です。
- 漢語調では:「冬至の候」「歳末の候」「歳晩の候」「月迫の候」など
- 口語調では:「冬至を過ぎ、いよいよ年の瀬も押し迫ってまいりました。」「今年も余日(よじつ)わずかとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。」など
- 時候の挨拶に続けて「ご自愛ください」や「良いお年をお迎えください」といった結びの挨拶を添えることが、特に年末の時期には重要です。
- 一年で最も昼が短い「冬至(とうじ)」を迎え、いよいよ年の瀬を迎える時期です。年末の慌ただしさや、一年間の感謝、新年の挨拶といった要素を含んだ表現が適切です。
また、12月は公私ともに区切りの多い月です。ビジネス文書では感謝やお礼を、私信では健康を気遣う言葉を添えると、丁寧で印象の良い挨拶文に仕上がります。
二十四節気「大雪」「冬至」「小寒」を意識する表現
12月には、季節の変化を示す二十四節気として「大雪(たいせつ)」「冬至(とうじ)」「小寒(しょうかん)」が含まれます。これらを意識した表現を用いることで、季節感のある洗練された文章になります。
大雪(たいせつ)
[12月7日頃]
- 山々に雪が降り積もり始める頃。
- 冬の寒さが本格化し、「大雪の候」「寒冷の候」などの挨拶がふさわしい時期です。
冬至(とうじ)
[12月22日頃]
- 一年で最も昼が短く、夜が長い日。
- ゆず湯やかぼちゃを食べる風習もあり、「冬至の候」「歳末の候」といった表現が用いられます。
小寒(しょうかん)
[1月5日頃]
- 暦上は1月の節気ですが、12月下旬から続く寒さのピークに重なる。
- 「小寒の候」も年末の挨拶として使うことがあります。
こうした二十四節気を取り入れることで、暦に沿った品格ある時候の挨拶が完成します。
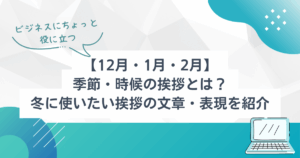
漢語調と口語調、それぞれの使い分けのコツ
12月はフォーマルな文書が増える時期であるため、目的に応じて「漢語調」と「口語調」を使い分けることが重要です。
| 項目 | 漢語調 | 口語調 |
|---|---|---|
| 特徴・メリット | ・格式が高く、文章に品格を与える ・ビジネスや公式文書にふさわしい ・季節感を簡潔に伝えられる | ・自然で親しみやすい ・柔らかい印象を与える ・相手への思いやりを表しやすい |
| 適した場面 | ・ビジネス文書 ・公式な挨拶状や案内状 ・礼儀を重んじる場面 | ・親しい取引先とのメール ・友人や家族宛ての手紙 ・カジュアルなやり取り |
| 12月の使用例 | 「初冬の候」 「寒冷の候」 「歳晩の候」 | 「寒さが身にしみる季節となりました」 「年の瀬を迎え、気忙しい日々が続きますね」 |
このように、12月の挨拶では季節の寒さだけでなく、一年の締めくくりを意識した温かな気遣いを添えることで、印象に残る挨拶文に仕上がります。
12月上旬に使える時候の挨拶
12月上旬は、暦の上で「大雪(たいせつ)」を迎える時期。
冬の訪れを実感しながらも、街にはまだ秋の名残が感じられます。仕事や学校、暮らしが一段と慌ただしくなる時期でもあり、挨拶文では「寒さ」と「年の瀬らしさ」をバランスよく伝える表現が好まれます。この時期は“季節の入り口”としての表現がポイントです。
漢語調の表現例:初冬の候、大雪の候、師走の候【使用目安:12月上旬~中旬】
12月上旬から中旬にかけては、冬の冷え込みが本格化し、年末に向けて街がにぎわいを見せる時期です。この時期の時候の挨拶では、冬の訪れと師走の忙しさを品よく伝える表現が好まれます。
「初冬の候」は冬の始まりを表す定番の言葉であり、「大雪の候」は二十四節気に基づく季節感のある表現であり、「師走の候」は、年末のあわただしさや一年の締めくくりを表す最もポピュラーな挨拶語として用いられています。
フォーマルな文書やビジネスのご挨拶では、これらの漢語調の表現を使うことで、格式と季節感を両立した印象的な文章に仕上げることができます。
| 表現 | 読み方 | 意味・ニュアンス | 使用目安 | 使用例 |
|---|---|---|---|---|
| 初冬の候 | しょとうのこう | 冬の始まりを意味する言葉。冷たい空気と静かな季節の訪れを上品に表現。 | 11月下旬~12月中旬 | 初冬の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。 |
| 大雪の候 | たいせつのこう | 二十四節気「大雪」に由来。冬の寒さが本格化する頃を表す。 | 12月7日頃~12月15日頃 | 大雪の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。 |
| 師走の候 | しわすのこう | 年末の慌ただしさを象徴する言葉。感謝や締めくくりの挨拶に適する。 | 12月上旬~下旬 | 師走の候、皆様お変わりなくお過ごしのことと存じます。 |
これらの漢語調の表現はいずれも、12月上旬から中旬にかけての挨拶文に広く使える定番の言葉です。
「初冬の候」は、冬の始まりを落ち着いた印象で伝えることができ、季節の移り変わりを上品に表現したいときに最適です。「大雪の候」は、二十四節気の一つである“大雪”に由来し、暦の上で冬本番を迎えた時期に使うことで、季節感のある格式高い印象を与えます。
また、「師走の候」は、年末の忙しさや一年の締めくくりを表す言葉として、ビジネス・私信を問わず非常に汎用性が高い表現です。
これらの挨拶語を用いる際は、続く一文で相手の健康や一年の労をねぎらう言葉を添えると、より丁寧で心のこもった文章になります。
たとえば、「ご多忙の折、どうぞご自愛くださいませ」「寒さ厳しき折、皆様のご健康をお祈り申し上げます」など、
季節感と気遣いの言葉を組み合わせることで、文章全体に温かみと品格が生まれます。
口語調の表現例:寒さが日に日に増してまいりました/師走を迎え何かと気ぜわしい毎日です
12月上旬から中旬にかけては、冬の寒さが日に日に厳しくなり、年末の忙しさを感じ始める頃です。この時期の口語調の挨拶では、寒さへの気遣いや一年の労をねぎらう言葉を自然に盛り込むことがポイントでしょう。
「寒さが日に日に増してまいりました」は、気温の低下を素直に伝える定番の表現で、ビジネスメールや手紙の冒頭にも使いやすい一文です。
一方、「師走を迎え何かと気ぜわしい毎日です」は、年の瀬の慌ただしさをやわらかく表現し、相手の近況を思いやる印象を与えます。
堅すぎず、かといってくだけすぎない——そんな口語調ならではの自然な言葉遣いが、12月の挨拶文をより温かみのあるものにしてくれるでしょう。
| 表現 | 意味・ニュアンス | 使用目安 | 使用例 |
|---|---|---|---|
| 寒さが日に日に増してまいりました | 冬の訪れを実感する頃に使う定番表現。ビジネス・私用どちらにも適する。 | 12月上旬~中旬 | 寒さが日に日に増してまいりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。 |
| 師走を迎え何かと気ぜわしい毎日です | 年末特有の忙しさや慌ただしさを伝える言葉。親しみと共感を生む表現。 | 12月上旬~下旬 | 師走を迎え何かと気ぜわしい毎日です。どうぞお体にお気をつけてお過ごしください。 |
これらの口語調の表現は、12月の冷え込みと年末の忙しさをやわらかく伝えるのに最適です。
「寒さが日に日に増してまいりました」は、冬の深まりを感じさせる定番の挨拶文であり、ビジネスでも私信でも違和感なく使える万能な一文です。
一方で、「師走を迎え何かと気ぜわしい毎日です」は、年末特有の慌ただしさを表現しながらも、どこか親しみを感じさせる言い回し。特に、相手の健康や無理のない生活を気遣う文面と組み合わせると、季節感と温かみが一層引き立ちます。
口語調の挨拶では、堅苦しさを避けつつも丁寧な言葉遣いを意識することが大切です。たとえば、文末に「どうぞお体に気をつけてお過ごしください」「本年も残りわずかとなりましたが、ご自愛くださいませ」と添えることで、
冬の寒さの中にもぬくもりを感じさせる挨拶文に仕上がります。
12月という一年の節目にふさわしい、穏やかで誠実な印象を与える表現として活用できるでしょう。
12月上旬に使える時候の挨拶の選び方
12月上旬は、「初冬の寒さ」と「年末の始まり」を意識した言葉選びがポイントです。
「初冬の候」や「大雪の候」は、寒さの始まりをフォーマルに伝えたいビジネス文書にぴったりの表現であり、「師走の候」は季節だけでなく“年の瀬の気忙しさ”を含むため、12月全般に使える便利な言葉です。
口語調では、「寒さ」「忙しさ」「気遣い」をバランスよく盛り込むのがポイント。たとえば「寒さが増してまいりました。どうぞお体を大切にお過ごしください。」のように、相手を気遣う一文を添えると、より温かみのある印象になります。
12月中旬に使える時候の挨拶
12月中旬は、日ごとに寒さが厳しくなり、街には本格的な冬の気配が漂う季節です。
日暮れが早まり、空気が一段と冷たく感じられるこの時期は、季節の移ろいとともに、相手の健康や一年間の労をねぎらう表現を取り入れると良いでしょう。12月中旬に用いる時候の挨拶としては、「寒冷の候」のように“冬の深まり”を意識するのがポイントです。
漢語調の表現例:寒冷の候、短日の候、師走の候、寒気の候
12月中旬は、一年の締めくくりが近づき、寒さがいっそう厳しくなる時期です。日暮れが早くなり、街のイルミネーションや年の瀬の雰囲気が冬の深まりを感じさせます。この頃の時候の挨拶には、寒さの厳しさと年末の静けさを上品に伝える漢語調の表現がふさわしいでしょう。
「寒冷の候」は冬の冷え込みを端的に表し、ビジネスでも私信でも使いやすい万能な表現。「短日の候」は“日が短い季節”という意味で、冬の情緒を穏やかに伝えたいときにぴったりです。また、「師走の候」「寒気の候」は、年の瀬のあわただしさと季節の厳しさを併せて表す言葉として広く使われます。
フォーマルな挨拶状や取引先への年末のご挨拶には、これらの表現を取り入れることで、気品と季節感のある文章に仕上がります。
| 表現 | 読み方 | 意味・ニュアンス | 使用目安 | 使用例 |
|---|---|---|---|---|
| 寒冷の候 | かんれいのこう | 寒さが厳しくなってきた時期を表現。冬の挨拶として最も一般的。 | 12月中旬~下旬 | 寒冷の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 |
| 短日の候 | たんじつのこう | 日が短く、夜が長くなった季節を表す。静けさを感じさせる表現。 | 12月中旬~下旬 | 短日の候、貴社いよいよご隆盛のことと拝察いたします。 |
| 師走の候 | しわすのこう | 年の瀬の忙しさと季節の寒さをあわせて表現できる便利な言葉。 | 12月全般 | 師走の候、何かとご多忙の折ではございますが、ご自愛くださいますようお願い申し上げます。 |
| 寒気の候 | かんきのこう | 冷たい空気に包まれる時期を表す。フォーマルな挨拶状に最適。 | 12月中旬~1月上旬 | 寒気の候、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。 |
これらの漢語調の表現は、12月中旬の寒さと年末の情景を端的に伝える定番の挨拶語です。
「寒冷の候」は、冬の厳しい寒さを示す最も一般的な表現であり、ビジネス文書や公式な挨拶状にも広く用いられます。
「短日の候」は、日が短く夜が長くなった季節を指し、静かな冬の趣を感じさせる上品な言葉であり、「師走の候」は一年の締めくくりを意味し、年末のご挨拶やお礼状などに最もよく使われる汎用性の高い表現といえるでしょう。
「寒気の候」は、冷たい空気に包まれる冬の厳しさを表現しながらも、落ち着いた印象を与える言葉で、改まった書面に最適な時候の挨拶です。
これらの語を使う際は、時候の挨拶に続けて「ご多忙の折、どうぞご自愛ください」「寒さ厳しき折、皆様のご健康をお祈り申し上げます」など、相手を気遣う一文を添えると、より丁寧で心のこもった印象になります。
寒さが深まる12月中旬の挨拶では、こうした漢語調の表現を使うことで、季節の厳しさと年末らしい落ち着きを上品に伝えることができるでしょう。
口語調の表現例:日暮れが早くなり、冬の深まりを感じる頃です/空気の冷たさが身にしみます
12月中旬は、日暮れの早さと冷たい空気に、冬の深まりを実感する季節です。
街中ではクリスマスの灯りがともり、慌ただしさの中にもどこか温かい雰囲気が漂う頃。この時期の口語調の挨拶では、季節の移ろいを穏やかに描きながら、相手の健康や日常を気遣う表現がふさわしいでしょう。
「日暮れが早くなり、冬の深まりを感じる頃です」は、季節の静けさを上品に伝える一文で、ビジネス文書にも使える柔らかな表現です。また、「空気の冷たさが身にしみます」は、寒さを体感的に表しつつも、相手を思いやる気持ちを自然に添えられるフレーズです。
12月中旬の口語調表現では、堅すぎず、季節の情緒と人への温かさを両立させた言葉選びがポイントです。
| 表現 | 意味・ニュアンス | 使用目安 | 使用例 |
|---|---|---|---|
| 日暮れが早くなり、冬の深まりを感じる頃です | 冬の季節感を穏やかに伝える表現。上品で落ち着いた印象を与える。 | 12月中旬 | 日暮れが早くなり、冬の深まりを感じる頃です。お元気でお過ごしでしょうか。 |
| 空気の冷たさが身にしみます | 冬らしい冷たさを表現しつつ、体調への気遣いを添えやすい一文。 | 12月中旬~下旬 | 空気の冷たさが身にしみます。どうぞお体にお気をつけてお過ごしください。 |
これらの口語調の表現は、12月中旬の冷たい空気や日暮れの早さといった冬の情景を、やわらかく伝えるのに適した言葉です。
「日暮れが早くなり、冬の深まりを感じる頃です」は、季節の移ろいを落ち着いた調子で表す一文であり、ビジネス・私信のどちらにも自然に使うことができます。また、「空気の冷たさが身にしみます」は、冬の厳しさを感じながらも相手を気遣う温かい印象を与える表現で、寒さの中にぬくもりを感じさせる挨拶として効果的です。
これらの文は、漢語調に比べて柔らかく親しみやすいため、社内文書や取引先への季節のメール、年末のご挨拶などにも使いやすいのが特徴です。
また、結びに「どうぞお体を大切にお過ごしください」「寒い日が続きますが、くれぐれもご自愛くださいませ」と添えることで、より丁寧で心のこもった挨拶文になります。
12月中旬のように寒さが深まる季節には、情景と気遣いを一文の中で自然に表現することが、読む人の心に温かさを残すコツです。
12月中旬に使える時候の挨拶の選び方
12月中旬は、一年の締めくくりが近づき、寒さが本格化する時期です。この時期の時候の挨拶では、「寒さの厳しさ」と「年末の忙しさ」を意識して言葉を選ぶと自然です。
「寒冷の候」や「寒気の候」は、フォーマルな手紙やビジネスメールにふさわしい定番表現。一方、「短日の候」は日照時間の短さを情緒的に伝えられるため、季節の深まりを穏やかに表現したい場合におすすめです。
また、口語調では「日暮れ」「空気」「冷たさ」といった体感的な要素を取り入れると、読む人に季節の情景をイメージさせる効果があります。
年の瀬に向けて、相手を思いやる言葉を添えると、より印象に残る挨拶文になるでしょう。
12月下旬に使える時候の挨拶
12月下旬は、一年の締めくくりにふさわしい時期。冬至を過ぎ、日が少しずつ長くなる一方で、寒さは一段と厳しさを増します。
年の瀬を迎えるこの時期は、相手の健康を気遣いながら、一年間の感謝を込めた挨拶が喜ばれます。
「12月下旬 時候の挨拶」「歳末の候 使い方」といった検索が多いように、この季節は“年末らしさ”を表す言葉選びが重要です。
漢語調の表現例:冬至の候、歳末の候、歳晩の候、年末厳寒の候、月迫の候
12月下旬は、一年の締めくくりとともに冬の寒さがいっそう厳しくなる時期です。
冬至を過ぎ、昼の短さと冷たい空気に季節の深まりを感じながら、街には年の瀬の慌ただしさが漂い始めます。この時期の時候の挨拶では、年末の静けさと感謝の気持ちを上品に伝える漢語調の表現がふさわしいでしょう。
「冬至の候」は、暦上で冬の折り返しを迎える時期に用いる季節感豊かな言葉で、「歳末の候」や「歳晩の候」は、一年を締めくくる挨拶としてビジネス・私信の両方に広く使われます。
また、「年末厳寒の候」や「月迫の候」は、年の終わりの寒さと慌ただしさを表す改まった表現で、改年の挨拶や感謝を伝える場面に最適です。
12月下旬の漢語調挨拶は、季節の厳しさの中に感謝と気遣いを込めることが大切です。年の瀬にふさわしい丁寧な言葉選びで、節目のご挨拶を上品に締めくくりましょう。
| 表現 | 読み方 | 意味・ニュアンス | 使用目安 | 使用例 |
|---|---|---|---|---|
| 冬至の候 | とうじのこう | 一年で最も昼が短い時期を表す。寒さの中にも希望を感じさせる表現。 | 12月20日頃~25日頃 | 冬至の候、皆様お健やかにお過ごしのこととお喜び申し上げます。 |
| 歳末の候 | さいまつのこう | 年の終わりを意味する定番表現。ビジネス・私信どちらにも使える。 | 12月中旬~31日頃 | 歳末の候、今年もご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 |
| 歳晩の候 | さいばんのこう | 年の暮れを上品に表す語。特にフォーマルな年末挨拶に適している。 | 12月20日頃~31日頃 | 歳晩の候、貴社いよいよご隆盛のこととお慶び申し上げます。 |
| 年末厳寒の候 | ねんまつげんかんのこう | 年末の厳しい寒さを強調した表現。力強く改まった印象を与える。 | 12月下旬~1月上旬 | 年末厳寒の候、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。 |
| 月迫の候 | げっせいのこう | 「月(年)が迫る」意から、年の瀬を表現する雅な言葉。 | 12月下旬 | 月迫の候、本年中のご厚情に心より感謝申し上げます。 |
これらの漢語調の表現は、12月下旬から年末にかけて使用される、格式と季節感を兼ね備えた時候の挨拶語です。
「冬至の候」は、一年でもっとも日が短くなる冬至の頃に使われる言葉で、冬の深まりと静けさを感じさせます。「歳末の候」や「歳晩の候」は、一年の締めくくりを意味し、ビジネス文書・年末のご挨拶・お礼状など、あらゆるフォーマルな場面に適した定番表現です。
また、「年末厳寒の候」は、冬の厳しい寒さと年の瀬の時期を重ね合わせた表現で、相手を思いやる丁寧な印象を与え、「月迫の候」は、“月が迫る”すなわち“年が押し迫る”という意味を持ち、やや文語的ながら、改まった挨拶文や儀礼的な書簡に用いると格調高くまとまります。
これらの表現を用いる際は、続く一文で「寒さ厳しき折、皆様のご健康をお祈り申し上げます」「ご多忙の折、くれぐれもお体をお大事にお過ごしください」など、相手の健康や一年の労をねぎらう言葉を添えるとより丁寧です。
12月下旬の挨拶文では、季節の厳しさを伝えながらも、感謝と気遣いを込めた温かい言葉選びを心がけることで、年末にふさわしい印象深い文章に仕上がります。
口語調の表現例:年の瀬も押し迫ってまいりました/今年も残りわずかとなりましたが、お変わりありませんか
12月下旬は、いよいよ一年の終わりが近づく「年の瀬」の季節。
街には慌ただしさと同時に、一年を振り返る静けさや温かい空気が漂い始めます。この時期の挨拶では、一年の労をねぎらい、相手への感謝と気遣いを伝える言葉を選ぶことが大切です。
「年の瀬も押し迫ってまいりました」は、年末の慌ただしさをやわらかく伝える定番の表現で、ビジネス文書にも私信にも違和感なく使えます。また、「今年も残りわずかとなりましたが、お変わりありませんか」は、相手の健康や近況を自然に気遣う一文として、親しみと誠意を両立させた表現です。
12月下旬の口語調の挨拶は、堅苦しさを避けつつも丁寧さを保つことがポイント。一年の感謝を込めて、心温まる言葉で締めくくると、読み手に好印象を与える季節の挨拶になります。
| 表現 | 意味・ニュアンス | 使用目安 | 使用例 |
|---|---|---|---|
| 年の瀬も押し迫ってまいりました | 一年の終わりが近いことを伝える定番表現。年末のご挨拶にぴったり。 | 12月下旬 | 年の瀬も押し迫ってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 |
| 今年も残りわずかとなりましたが、お変わりありませんか | 一年を振り返りながら、相手の近況を気遣うやさしい表現。 | 12月20日頃~31日頃 | 今年も残りわずかとなりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。 |
| 寒さが一段と厳しくなってまいりました | 寒冷の季節を感じさせる汎用的な挨拶。年末にも使える。 | 12月下旬~1月初旬 | 寒さが一段と厳しくなってまいりました。どうぞご自愛のうえ、よいお年をお迎えください。 |
これらの口語調の表現は、年末のあわただしさの中にも相手を思いやる温かさを伝える言葉としてよく使われます。
「年の瀬も押し迫ってまいりました」は、年末特有の慌ただしさを穏やかに表現する一文で、ビジネスメールやお礼状など、さまざまな場面で使いやすい定番の挨拶です。一方、「今年も残りわずかとなりましたが、お変わりありませんか」は、季節の区切りに加え、相手の健康や日々の安寧を気遣う丁寧な印象を与える表現です。
これらの文は、堅苦しすぎず、かといってくだけすぎない絶妙なバランスを保ちながら、年末の節目にふさわしい親しみと誠実さを伝えられるのが特徴です。
文末には「本年もお世話になり、誠にありがとうございました」「新しい年が皆様にとって良い一年となりますようお祈り申し上げます」など、一年の感謝や新年への願いを添えると、より温かみのある印象に仕上がります。
12月下旬の口語調の挨拶では、感謝・労い・気遣いの3要素を自然に盛り込むことで、形式にとらわれない心のこもった季節の挨拶文を作ることができます。
12月下旬に使える時候の挨拶の選び方
一年の感謝を伝えるとともに、相手の健康や新年への願いを込める時期です。「歳末の候」「歳晩の候」は、年の終わりを上品に表す漢語調の定番表現で、年賀状前の挨拶状やビジネスレターにも最適です。
「冬至の候」は季節的な情緒を添えたいときに使いやすく、「月迫の候」は少し文学的な味わいを出したい場面にぴったりです。
一方、口語調では「年の瀬も押し迫ってまいりました」「今年も残りわずかとなりました」など、自然な語り口と感謝の気持ちを組み合わせるのがポイント。
ビジネスでは「本年中のご厚情に感謝申し上げます」と続けると、より丁寧で印象の良い文章になります。
この時期は、一年を労い、新年への期待を込めた言葉で締めくくることが大切です。
時候の挨拶でよくある誤用と注意点
12月は季節の節目であり、暦の上では冬本番を迎える時期です。
しかし、実際の気候や地域の違いによって体感はさまざまで、時候の挨拶を使う際には細やかな配慮が求められます。ここでは、誤用しやすいポイントとその対策をまとめました。
二十四節気と実際の気候ズレに注意:雪が降らない年もあり得る
12月の二十四節気には「大雪(たいせつ)」や「冬至(とうじ)」がありますが、地域によっては雪が降らない、または寒さがそれほど厳しくない年もあります。
そのため、「大雪の候」「厳寒の候」などの表現を使う際は、その年の天候や地域の状況を踏まえて選ぶことが大切です。
実際の体感と合わない表現を使うと、やや不自然な印象になることがあるため注意しましょう。
表現の重複に注意:同じ「師走の候」などを書き出し・結びで使わないように
「師走の候」「歳末の候」などは12月の代表的な挨拶言葉ですが、文頭と文末で同じ表現を繰り返すのは避けるのがマナーです。
たとえば、冒頭に「師走の候」を使った場合は、結びには「寒さ厳しき折」「年の瀬を迎え」など、別の言葉に置き換えると文章に変化が出ます。
同じ語を繰り返すと硬い印象や冗長さを与えるため、冒頭と締めで異なる季節語を使い分けるのが上級の書き方です。
地域差・気温差を配慮:寒冷感や日暮れの早さは地域によって感じ方が違う
日本は南北に長く、地域によって季節の進み方に大きな差があります。
たとえば北海道や東北ではすでに雪景色でも、九州や四国ではまだ紅葉が残る時期です。そのため、全国に向けた挨拶やビジネス文書では、「寒さがいっそう厳しくなってまいりました」「冬の訪れを感じる頃です」など、幅広い地域に対応できる表現を選ぶと安心です。
また、相手の居住地がわかっている場合は、その地域の気候に合わせた一文を添えると、より丁寧で心のこもった印象になります。
12月の時候の挨拶では、暦の正確さよりも「実際の季節感」と「相手への思いやり」を大切にすることがポイントです。言葉の美しさだけでなく、相手がその季節をどう感じているかを意識して表現を選びましょう。
まとめ:12月の時候の挨拶早見表
一年の締めくくりとなる12月は、冬の寒さが本格化し、街も人も慌ただしく動き始める季節です。
この時期の挨拶文では、季節の厳しさを伝える言葉とともに、一年の感謝や相手を思いやる気持ちを込めることが大切です。
- 上旬は「初冬」や「師走」など、冬の訪れを感じさせる言葉
- 中旬は「寒冷」「短日」など、冷たく澄んだ空気を表す表現
- 下旬は「歳末」「年末厳寒」など、年の瀬らしい表現
上記を意識した言葉を使うと、自然かつ丁寧なコミュニケーションになるでしょう。
以下の早見表では、「12月 時候の挨拶 一覧」として、上旬・中旬・下旬それぞれにふさわしい漢語調と口語調の代表的な表現をまとめています。ビジネス文書・年賀状・お礼状・メールなど、さまざまなシーンで使える参考例としてご活用ください。
| 時期 | 漢語調(格式高い表現) | 口語調(やわらかい表現) | 季節の特徴 |
|---|---|---|---|
| 上旬(~12月10日頃) | 初冬の候/大雪の候/師走の候 | 寒さが日に日に増してまいりました/師走を迎え何かと気ぜわしい毎日です | 冬の始まりを感じる時期。朝晩の冷え込みが強まり、年末の忙しさを意識し始める。 |
| 中旬(12月11日~20日頃) | 寒冷の候/短日の候/師走の候/寒気の候 | 日暮れが早くなり、冬の深まりを感じる頃です/空気の冷たさが身にしみます | 一年の締めくくりに向けて慌ただしさが増す時期。日照時間が短く、寒さも本格化。 |
| 下旬(12月21日以降) | 冬至の候/歳末の候/歳晩の候/年末厳寒の候/月迫の候 | 年の瀬も押し迫ってまいりました/今年も残りわずかとなりました | 冬至を過ぎて寒さが最も厳しくなる時期。年末の挨拶や一年の感謝を伝える言葉が中心。 |
12月は一年を締めくくる月として、感謝や労いの気持ちを表す表現が重要になります。
ビジネスでは「歳末の候」「年末厳寒の候」などの漢語調で格式を保ち、親しい相手には「今年も残りわずかとなりました」「寒さが身にしみる季節です」といった口語調で温かみを添えると良いでしょう。
その年の気候や相手との関係に合わせて言葉を選ぶことで、年末のご挨拶がより丁寧で印象深いものになるのではないでしょうか。