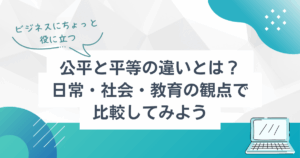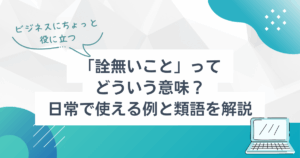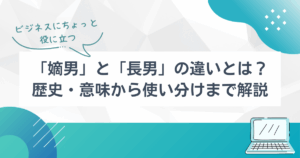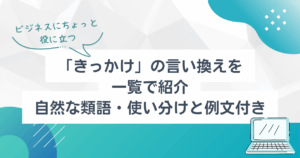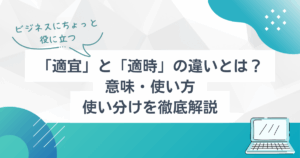経営理念をカタチに!心に響く職場スローガンの作り方と有名企業の実例集

企業の成長やチームの団結に欠かせないのが「職場スローガン」です。単なるキャッチフレーズではなく、経営理念や組織の価値観を社員一人ひとりの心に浸透させる役割があること、ご存知でしょうか。
心に響くスローガンは、社員のモチベーションを高めるだけでなく、顧客や社会に対して企業姿勢を明確に伝える力も持っています。そこで本記事では、効果的なスローガンの作り方から、有名企業の成功事例までをわかりやすく解説します。これからスローガンづくりに取り組む経営者や人事担当者の方にとって、実践的なヒントになれば幸いです。
そもそもスローガンとは?職場における意義と役割
職場におけるスローガンは、単なる「決まり文句」ではなく、組織の方向性や価値観を一言で表す重要なメッセージです。会社の理念を分かりやすく伝え、社員の意識を統一することで、組織全体に活力を与える役割があるといえるでしょう。まずは、スローガンの基本的な意味と、その目的についてご紹介いたします。
スローガンとは何か?理念を一言で伝える旗印
スローガンとは、企業や組織が掲げる理念や目標を短く凝縮した言葉です。
長い経営理念や複雑な方針を、誰もが覚えやすいシンプルな表現に落とし込むことで、日常業務の中でも常に意識しやすくなります。いわば「旗印」として、組織がどの方向へ進むべきかを示す役割を果たしているのです。
スローガンの特徴
- 経営理念やビジョンを短い言葉に凝縮
- 社員全員が覚えやすく共有しやすい表現
- 社内外に対して「この会社は何を大切にしているか」を明示
スローガンは単なる言葉ではなく「企業文化を象徴する言葉」として機能すると考えられます。
スローガンの目的:チームの一体感と行動指針を育む
スローガンの大きな目的は、チームの一体感を高め、日々の行動に一貫性を持たせることにあります。言葉の力によって社員が共通の目標を意識できれば、組織はより強固にまとまり、成果に向かって進むことができます。
スローガンを決めることで生まれる4つの効果
- 一体感の醸成:共通の言葉を持つことで、社員同士の結束が強まる
- 行動の指針:迷ったときに立ち返る基準として機能する
- モチベーション向上:ポジティブな言葉が日常業務を後押しする
- 外部への発信:顧客や取引先に、組織の姿勢をシンプルに伝える
このようにスローガンは、単なる合言葉ではなく、組織の成長と信頼を支える「言葉の土台」として重要な役割を担っているのです。
スローガンと経営理念(MVV)の関係
職場スローガンを考える際に欠かせないのが、企業の根幹をなす「MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)」とのつながりです。
スローガンはミッション・ビジョン・バリューの一部を切り取ったり、よりシンプルに表現することが多いです。ここではまずMVVの基本構造を整理し、そのうえでスローガンとの関係性を解説します。
ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)の構造
MVVとは、企業活動の基盤となる3つの要素を指します。これらは組織文化を形づくり、全ての意思決定や行動のよりどころになります。
- ミッション(Mission):企業が存在する目的。「何のために存在するのか」を明確にする
- ビジョン(Vision):企業が目指す未来像。「どこへ向かうのか」を示す
- バリュー(Value):社員が共有すべき価値観や行動規範。「どう行動するか」を定める
この三位一体の枠組みを理解することで、スローガンがどこに位置づけられるのかが明確になります。つまりスローガンは、MVVを一言で体現した「エッセンス」とも言えるかもしれません。
スローガンとMVVの整合性が信頼を生む
効果的なスローガンをつくるには、MVVとの一貫性もしくは関係性が欠かせません。
もしスローガンがMVVから外れてしまうと、社員の混乱を招いたり、顧客からの信頼を損ねたりするリスクがあります。逆に、MVVを正しく反映したスローガンは、社内外に強い説得力を持ちます。
スローガンとミッション・ビジョン・バリューの整合性が取れていると
- 社内への効果:社員が日常的に触れるスローガンを通じて、理念が自然と浸透する
- 社外への効果:顧客やパートナーに、企業の姿勢をシンプルに伝え、共感を呼ぶ
上記のような効果が期待できます。
たとえば「挑戦を恐れない」というバリューを掲げている企業が「Always Challenge」というスローガンを掲げれば、メッセージに一貫性があり、信頼感を高めやすいでしょう。
このように、スローガンはMVVを補完し、わかりやすく伝えるための機能も持っています。
職場のスローガンはどう作る?魅力的にするためのコツは?
魅力的で効果的なスローガンをつくるには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。単に響きの良い言葉を並べるのではなく、組織の目的や社員の心に深く届くメッセージであることが重要です。ここでは、スローガン作成の具体的なコツを紹介します。
ターゲットと目的を明確にする(誰に・何を伝えるか)
スローガンづくりの第一歩は「誰に向けて、どのようなメッセージを届けたいのか」をはっきりさせることです。社員向けなのか、顧客向けなのかによって、言葉の選び方は大きく変わります。
- 社員向け:組織の一体感を高め、日々の行動を後押しする言葉
- 顧客向け:企業の姿勢や提供価値を端的に表すフレーズ
- 社会向け:CSRや理念を社会全体に訴求するメッセージ
ターゲットが不明確なままでは、スローガンが空回りしてしまう可能性があります。
短く、覚えやすく、響きを意識した言葉選び
スローガンは「一度聞いたら忘れない」くらいのシンプルさが求められます。長すぎたり複雑な言葉を用いたりすると、記憶に残りにくくなってしまいます。
そのため、
- 短くシンプルに:5~10文字程度が理想的
- リズムや響きを重視:繰り返しや韻を取り入れると印象的になる
- 日常で使いやすい表現:会話の中でも自然に使える言葉
こうした工夫により、スローガンが組織内で日常的に活用されやすくなります。
オリジナリティと普遍性を兼ね備える
効果的なスローガンは、他社との差別化を図るオリジナリティと、誰もが共感できる普遍性の両方を兼ね備えています。ユニークすぎて理解されないものや、逆にありきたりで埋もれてしまうものは避けるべきです。
たとえば、「変化を楽しむ」という言葉は多くの人に共感されやすい一方で、その表現を自社の文化やビジョンに即して工夫すれば、オリジナリティが生まれます。
ポジティブな表現を心がけ、メッセージ性を込める
スローガンは社員や顧客に前向きな印象を与えるものでなければなりません。
そのため、否定的な言葉ではなく、希望や行動を促す表現を選ぶことが大切です。
- 「できない」より「できる」
- 「禁止」より「挑戦」
- 「失敗回避」より「成長促進」
ポジティブで明るい言葉は、人々の気持ちを引き上げ、自然と行動につながっていくでしょう。単なるスローガンではなく、組織を動かす「エネルギー源」となる言葉を意識することが重要です。
スローガン作成のステップ:実践できるフローをご紹介
効果的なスローガンを作るには、思いつきではなく段階を踏んだプロセスが不可欠です。組織の理念や目標を反映しつつ、社員と顧客の心に残る表現を生み出すには、次の5つのステップを踏むと整理がしやすいので、ご参考になれば幸いです。
経営理念や経営者の想いを整理する
スローガンの出発点は、経営理念や経営者が抱く想いの言語化です。
企業が大切にしている価値観や存在意義を明確にしなければ、形だけのフレーズになってしまいます。
- 企業の「存在理由」を改めて確認する
- 経営者が語る未来像をキーワード化する
- 社員にとって誇れるポイントを整理する
この整理作業が、その後のすべてのステップの基盤となります。
ブレインストーミングで候補を収集
理念を整理したら、次に幅広い候補を出す段階です。部署を超えたメンバーでブレインストーミングを行い、多様な視点から言葉を引き出しましょう。
- 数を重視し、質は後から検討する
- キーワードを連想ゲームのように広げる
- 社員のリアルな声も積極的に反映する
このプロセスによって、意外な表現や斬新な発想が生まれることも少なくありません。
言葉を絞り込み、響きやリズムを検討
集めた候補を整理し、複数の軸で評価していきます。ここでは「覚えやすさ」「響きの良さ」「理念との一貫性」を意識することが重要です。
- 短くリズムのある言葉を優先する
- 発音しやすく、会話に自然に溶け込むかを確認
- 社員や顧客にとって誤解のない表現かどうかを精査
この段階で最終候補を2〜3案に絞り込みます。
経営陣と共有・合意形成を行う
スローガンは企業を象徴する言葉であるため、経営陣の合意は不可欠です。経営理念との整合性や社会的な発信力を踏まえ、トップの意思決定を仰ぎましょう。
- 候補案を経営陣に提示し、議論する
- 理念や戦略との一貫性を再確認する
- 経営者自身が納得して発信できるかを重視する
経営陣の承認を得ることで、スローガンが単なる「言葉」から「組織の旗印」へと昇華します。
社内外へ浸透させるための施策まで見据えた仕上げ
最後に大切なのは、決定したスローガンをどのように浸透させるかです。
言葉だけで終わらせず、日常業務や社外コミュニケーションに自然に組み込む工夫が求められます。
例えば、
- 社内イベントや研修でスローガンを繰り返し伝える
- 社員証、社内ポスター、イントラネットなどに掲載する
- ホームページや広告、商品パッケージに活用する
このような取り組みにより「言葉を作って終わり」ではなく、「言葉を生かして文化にする」ことに繋がり、スローガンづくりの最終ゴールと言えるでしょう。
具体的なスローガンの例:有名企業の事例を解説
有名企業のスローガンは、シンプルで覚えやすいだけでなく、その企業の理念やブランドイメージを的確に言葉にしています。
ここでは、代表的な事例を紹介しながら、どのように企業姿勢を表現しているのかを見ていきましょう。
サントリーのスローガン・コーポレートメッセージ
サントリーはコーポレートメッセージとして
「水と生きる」
という言葉を用いています。
これは、自然の恵みである水を企業活動の源泉と位置づけていると考えられます。
環境保全や社会貢献の姿勢を打ち出し、消費者に安心感を与えると同時に、従業員には「自分たちの仕事が社会や自然に直結している」という誇りを与えているのではないでしょうか。
従業員の働き方としても、環境意識や持続可能性を大切にする文化が育まれていると感じます。ソニー
パナソニックのスローガン・コーポレートメッセージ
パナソニックグループはブランドスローガンとして
「幸せの、チカラに。」
を打ち出しています。これは、変化し続ける世界の中で「お客様に寄り添い、持続可能な幸せを生み出す“チカラ”であり続けたい」というメッセージが込められていると感じます。
従業員の視点からすると、自分の業務が「幸せを生み出す力」になっていると感じられることで、仕事が単なる作業ではなく「社会的意義を持つもの」と捉えやすくなるのではないでしょうか。
富士フイルムのスローガン・コーポレートメッセージ
富士フイルムでは、コーポレートスローガンとして
「Value from Innovation」
を掲げています。
これは、 「イノベーション=新しい発想や技術への挑戦」がスローガンの核であるため、従業員は「現状維持ではなく変革に挑むこと」が評価されやすい土壌を意識できる言葉になっていると考えられます。
つまり、従業員に 挑戦・柔軟性・顧客価値志向を根づかせ、富士フイルムがフィルム事業から医療・ライフサイエンス・化粧品へと転換できた背景にも直結しています。単なる合言葉ではなく、日常の意思決定やキャリア形成にまで影響を与える強いメッセージです。
日立製作所のスローガン・コーポレートメッセージ
日立製作所のスローガンは、多くの方が聞いたことがあると思われる
「Inspire the Next」
とされています。
直訳すると「次をつなぐインスピレーションを」という意味合いで、未来に向けて革新や価値を創造する姿勢を示しています。
従業員に 未来志向・社会的使命感・挑戦意欲を持たせるスローガンになっているのではないでしょうか。単なる企業ブランディングではなく、日々の仕事で「次を見据えた行動」を促し、社員一人ひとりが未来の社会に貢献する姿勢を意識させる効果があります。
ホンダのスローガン・コーポレートメッセージ
Hondaは、2001年から「The Power of Dreams(夢の力)」をグローバルブランドスローガンとして掲げ、世界中に発信してきました。2023年4月には、このスローガンを再定義し、新たに「How we move you.(あなたを動かす力)」という副文を加えて発表しています。
「The Power of Dreams How we move you」
グローバルに共通したメッセージを持つことで、国や部門を超えて社員同士が同じ目的を共有できるようになると思われます。
言葉に込められた意味としては、
- The Power of Dreams(夢の力)
- 夢を持ち、それを形にすることがHondaの原動力
- 従業員に「挑戦」と「創造性」を促すメッセージ
- How we move you.(あなたを動かす力)
- 移動手段の提供にとどまらず、人の心を動かす体験を生み出す姿勢
- 顧客との感動や共感を大切にするHondaのブランド姿勢を表現
それぞれ上記のようなところでしょうか。
Honda全体として一体感が強まり、世界中の従業員が「夢と感動を社会に届ける」という共通の使命感を持って働くことができるスローガンです。
三菱電機のスローガン・コーポレートメッセージ
三菱電機では、コミットメントとして
「Changes for the Better」
を打ち出しています。
直訳すると「より良い変化を」という意味で、社会・顧客・従業員に対して前向きな進化を約束するメッセージとなっています。
従業員に「常に改善を続け、より良い成果を目指す姿勢」を促すことができます。現状にとどまらず挑戦する文化を育み、社会や顧客にとって価値ある変化を生み出す責任感を強める効果がありそうです。
NTTドコモのスローガン・コーポレートメッセージ
NTTドコモグループは、2024年11月7日よりブランドスローガンを新しくしており
「つなごう。驚きを。幸せを。」
となっています。これは「つなぐ」ことを価値創造の源泉とし、事業やパートナーをつなぎながら新たな価値を生み出し、驚きと幸せにあふれた社会を実現したいという意志を表現しています。
従業員に対しては、「つなぐこと」を価値創造の出発点として意識させ、通信技術だけでなく、人と人、企業と社会をつなぐ役割を担うことで、社員は自分の仕事が社会に驚きと幸せを届けることができる、と伝えているのえはないでしょうか。
ユニクロ(ファーストリテイリング)のスローガン・コーポレートメッセージ
大きな事業としてユニクロを持つファーストリテイリングでは
「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」
上記メッセージをステートメントとしてしています。これは「服」という日常に身近なものを起点に、社会や世界に革新をもたらすという強いメッセージに感じます。
従業員に向けては「変化を恐れず挑戦する姿勢」を意識させるメッセージとも取れます。また、グローバル展開を背景に「世界基準で成果を出す意識」や「持続可能性を意識した責任ある働き方」が根づきやすくなるのではないでしょうか。
ZOZOのスローガン・コーポレートメッセージ
ZOZOでは、下記の言葉をサステナビリティステートメントとして打ち出しています。
「ファッションでつなぐ、サステナブルな未来へ。」
このステートメントは、従業員に「ファッションを通じて社会をより良くする使命」を意識させていそうです。
日々の業務やサービス開発において、単に便利・楽しいだけではなく、環境・多様性・未来への責任を考慮する働き方を促す役割があるといえます。
セブン&アイ・ホールディングスのスローガン・コーポレートメッセージ
セブン&アイホールディングスでは、
「変化への対応と基本の徹底」
上記スローガンのもと、社会や顧客ニーズの変化を新たなチャンスと捉え、常に革新を推し進める姿勢と、業務の基礎やサービス品質を揺るぎなく継続する重要性を両立する意思を掲げています。
従業員に常に社会や顧客ニーズの変化を敏感に捉え、柔軟かつ迅速に行動する姿勢を求めています。同時に、接客や商品管理といった業務の基本を揺るぎなく徹底することで、品質や信頼を守り続ける意識を強めていると考えられます。
ローソンのスローガン・コーポレートメッセージ
ローソンは
「マチのほっとステーション」
上記をスローガンとしています。
背景として単なる「コンビニ」としての存在を超え、まちの人々が「ほっとできる場所」になることを目指しているようです。地域の日常に寄り添い、誰もが安心できる、ぬくもりあふれる拠点としてローソンが機能することを象徴するメッセージといえるでしょう。
また、「圧倒的な美味しさ」「人への優しさ」「地球(マチ)への優しさ」という3つの約束を掲げ、その実現を通じて「ほっと」した気持ちを提供する場であることを追求しています。これらはすべて、「マチの“ほっと”ステーション」という理念に共通していると感じます。
日本航空(JAL)のスローガン・コーポレートメッセージ
日本航空(JAL)では、
「明日の空へ、日本の翼」
をスローガンとして掲げています。
このメッセージから、「自分たちの仕事が未来の航空業界と日本を代表する翼を支えている」という強い誇りと責任感が感じ取れます。
「明日の空へ」という言葉は、日々の業務の中でも常に新しい挑戦や改善を続ける姿勢を促し、「日本の翼」という表現は、安全・安心を守りながら世界に誇れるサービスを提供する使命を従業員に自覚させます。
その結果、社員一人ひとりが、未来を見据えた成長とグローバル水準のホスピタリティを実現する働き方に繋がるのではないでしょうか。
社内へのスローガン浸透の工夫
どんなに優れたスローガンを作っても、社員に浸透しなければ意味がありません。
日常業務の中で自然に意識され、行動につながるように仕掛けることが大切です。ここでは、社内にスローガンを定着させるための具体的な工夫を紹介します。
朝礼や社内研修で全員が口にする習慣に
スローガンを社員全員が繰り返し口にすることで、自然と意識に刷り込まれます。朝礼やミーティングの冒頭で唱和したり、研修プログラムに組み込むのも効果的です。
- 毎日のルーティンに組み込むことで定着が早まる
- 新入社員研修で早期に浸透させる
- 部署単位での共有や唱和を習慣化する
「言葉にする」習慣が、組織文化を強化する基盤となります。
オフィスへの掲示や社内報で再認識の機会を増やす
視覚的にスローガンを目にする機会を増やすことも重要です。
例えば、オフィスの壁や会議室、デスク周りにポスターを掲示するだけでなく、社内報やイントラネットで定期的に紹介すると効果的でしょう。
- 社員証やノベルティに印字して身近に置く
- デジタルサイネージやスクリーンセーバーで表示
- 社内報でスローガンに関連したストーリーを特集
こうした工夫は「意識しなくても自然に目に入る環境」をつくり、浸透を後押しします。
経営者が模範となる行動で信頼を強めることが重要
スローガンを単なる「言葉」で終わらせないためには、経営者自身がその理念を体現することが欠かせません。
トップが実際にスローガンに沿った行動を示すことで、社員の信頼感は大きく高まります。
- 社長や役員がスローガンを意識した発言をする
- 社員への評価やフィードバックにスローガンを絡める
- スローガンに基づいたエピソードを積極的に共有する
経営者の姿勢が「お手本」となることで、スローガンは単なる言葉ではなく「実践的な行動指針」として組織に根づいていくのです。
まとめ:スローガンは企業文化を形づくる力強い言葉
職場スローガンは、経営理念をシンプルに表現し、社員や顧客に一貫したメッセージを届けるための重要なツールです。
本記事では以下のポイントを整理しました。
- スローガンは理念を一言で示す「旗印」であり、組織の一体感や行動指針を育む
- MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)との整合性が、信頼感を高める鍵となる
- 短く覚えやすく、ポジティブでオリジナリティある言葉が効果的
- 作成は理念整理から始まり、候補収集 → 絞り込み → 経営陣の合意 → 浸透施策へと進める
- 社内への定着には、習慣化・視覚化・経営者の模範行動が欠かせない
有名企業の事例からもわかるように、心に残るスローガンは単なるコピーではなく、企業の姿勢そのものを映し出す存在です。
自社らしさを反映したスローガンをつくり、文化として根づかせることで、組織の力をより一層引き出せるでしょう。