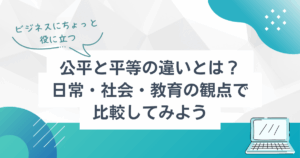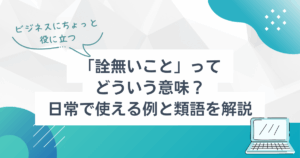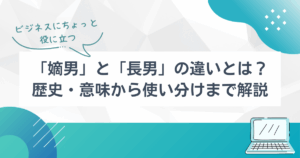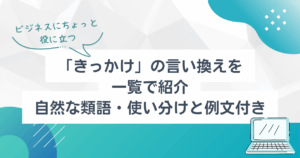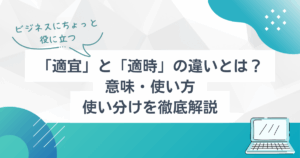ハラスメントをなくすために自分ができること【見かけたらどうする?】

職場や学校、日常の人間関係の中で、誰かがハラスメントを受けている現場に居合わせたことはありませんか?
「自分には関係ない」「何もできない」と感じて黙ってしまった経験がある人も多いかもしれません。しかし、見て見ぬふりが状況を悪化させることも事実です。
この記事では、ハラスメントの現場を“見かけたとき”に私たち一人ひとりができる具体的な行動について解説します。大きな勇気や特別な知識がなくても、誰かを守ることはできる——そんなヒントをお届けします。
ハラスメントとは?まずは“知る”ことから始めよう
ハラスメントをなくすための第一歩は、「正しく知ること」です。
言葉や態度が相手にどのような影響を与えるのかを理解することで、無意識の加害を防ぐことができます。特に、職場や学校などの組織では「これはハラスメント?それとも正当な指導?」と線引きが曖昧になりがちです。ここでは、代表的なハラスメントの種類と、それが適切な指導とどう違うのかについて見ていきましょう。
ハラスメントの種類と特徴
ハラスメントにはさまざまな種類があり、それぞれに特有の特徴があります。以下は代表的な例です。
- パワーハラスメント(パワハラ)
上司が部下に対して行う精神的・身体的な圧力。業務の範囲を超えた命令や叱責などが含まれます。 - セクシャルハラスメント(セクハラ)
性的な言動や視線、身体的接触などにより、相手に不快感や屈辱を与える行為。 - マタニティハラスメント(マタハラ)
妊娠・出産・育児に関する差別的扱いや不利益な発言・対応。 - モラルハラスメント(モラハラ)
無視・否定・人格否定など、言葉による精神的な攻撃を中心とするもの。 - アルコールハラスメント(アルハラ)
飲酒の強要や、飲めない人への配慮を欠いた態度など。
これらの行為は、加害者に悪意がなくても「受け手がどう感じたか」が判断基準となるため、非常に注意が必要です。
また、近年ではカスタマーハラスメントも社会問題になっています。下記コラム記事で解説していますので、併せてご一読いただければ幸いです。

指導との違いを理解する
ハラスメントと適切な指導の違いを見極めることも、重要なポイントです。以下のような基準を参考にするとよいでしょう。
| 項目 | 適切な指導 | ハラスメント |
|---|---|---|
| 目的 | 業務改善や人材育成 | 感情のはけ口や支配欲 |
| 方法 | 具体的で建設的な助言 | 抽象的で威圧的な言動 |
| 相手の尊重 | あり(対話を重視) | なし(否定や嘲笑) |
| 継続性 | 一時的 | 長期間にわたる |
たとえば、業務上のミスを指摘する際に、冷静に問題点を伝え改善策を話し合うのは指導ですが、大声で怒鳴ったり人格を否定するような言葉を投げかけるのはハラスメントにあたります。
このように、指導とハラスメントの違いを理解することで、自分自身の言動を客観的に見直すことができるようになります。
まず自分でできること:ハラスメントを受けたときの対処法
ハラスメントを受けたと感じたとき、「どうすればいいのかわからない」と戸惑う方も多いはずです。
しかし、被害を放置すれば精神的なダメージは蓄積し、状況は悪化してしまいます。そこで大切なのが、被害を最小限に抑えるための“セルフディフェンス”です。ここでは、自分で今すぐできる3つの対処法を紹介します。
嫌な言動には「NO」を伝える:アサーティブコミュニケーション
ハラスメントを受けたとき、はっきりと「それはやめてください」と伝えることが重要です。ただし、感情的に反応するのではなく、「自分の気持ちを正直に、かつ相手を傷つけずに伝える」アサーティブコミュニケーションがポイントです。
アサーティブな伝え方の例
- 「そう言われると私は不快に感じます」
- 「その話題はやめていただけますか?」
- 「私はこう感じたので、今後は控えてほしいです」
このように、自分の感情や意見を尊重しながら、相手に理解を求める姿勢が、関係悪化を避けつつ自己防衛につながります。
どうしても言えない…そんなときは無理をしないで
「NOを伝えることが大事」とはいえ、状況によってはそれが難しいこともあります。
特に相手が上司や権力を持つ人物であったり、過去に声を上げたことでハラスメントが悪化した経験がある場合、「はっきり言う」ことがかえってリスクになるケースもあります。
そのようなときは、無理に一人で解決しようとせず、別の手段で自分を守ることが大切です。
- まずは信頼できる同僚や友人に相談してみる
- 職場のハラスメント相談窓口に匿名で情報提供する
- 自分の気持ちをメモや日記に書き出し、状況を整理する
記録を取る習慣を持つ
ハラスメントの証拠を残すことも、重要な自己防衛策のひとつです。ハラスメントでよく問題になる「言った・言わない」の水掛け論を避けるために、以下のような情報を日常的に記録しておきましょう。
メモに記載すべき事項
- 発生日時と場所
- 発言の内容や状況
- 関係者や目撃者の有無
- その時の自分の気持ちや反応
スマートフォンのメモ機能や日記アプリを使えば、無理なく継続できます。万が一、第三者への相談や法的手段が必要になった際にも、有力な証拠となります。
相談先をあらかじめ確認しておく
いざという時に備えて、信頼できる相談先を事前に把握しておくことも重要です。社内外に目を向けて、複数の選択肢を確保しておくと安心です。
ハラスメントが起こったときの相談先例
- 会社の人事部やコンプライアンス窓口
- 労働組合
- 外部のハラスメント相談窓口(自治体やNPOなど)
- 産業医やカウンセラー
また、信頼できる同僚や友人に相談するだけでも、気持ちが軽くなることがあります。ひとりで抱え込まず、「声を上げてもいいんだ」と自分に許可を出すことが、最初の一歩になるでしょう。
ハラスメントの加害者にならないために心がけること
ハラスメントの加害者になるつもりはなくても、「そんなつもりはなかった」という言葉では済まされないケースが多くあります。
立場や状況によっては、自分の何気ない言動が他人を深く傷つけていることもあるのです。だからこそ、誰もが「自分が加害者にならないための意識」を持つことが必要不可欠です。以下では、日常的に心がけたい3つのポイントを紹介します。
自分の言動を客観的に振り返る
まず重要なのは、自分の発言や行動が他人にどう受け取られているかを客観的に見直す習慣を持つことです。
- 相手が笑っていなくても「冗談だった」と済ませていないか?
- 立場の弱い人にだけ強い口調で接していないか?
- 「前も言ったよね?」という表現で威圧していないか?
他者の反応を注意深く観察し、違和感を覚えたら立ち止まって考える姿勢が、加害の芽を摘む第一歩となります。
価値観を押し付けない、人を尊重する態度を
自分にとって「普通」「常識」だと思っていることも、他人にとってはそうでない場合があります。特にジェンダーや文化、年齢による価値観の違いには敏感になる必要があります。
- 「男なんだからもっと強くなれよ」
- 「女のくせに泣くなんて甘えてる」
- 「若いんだから我慢しろ」
こうした言葉には、無意識の偏見や固定観念が含まれていることが多く、受け手にとっては差別的・侮辱的に感じられる可能性があります。大切なのは、「違っていて当たり前」という前提で人と接することではないでしょうか。
「指導」と「ハラスメント」の境界を意識する
上司や先輩など、誰かを育成・指導する立場にある人ほど、「これは適切な指導なのか?」と自問する姿勢が求められます。
- 感情的に怒鳴ってしまう
- 他の人がいる前で叱責する
- 同じミスを繰り返し責め立てる
指導とは、相手の成長を促すための建設的なコミュニケーションです。
恐怖やプレッシャーによって行動を変えさせようとする方法は、結果的にハラスメントとみなされるリスクが高くなります。指導においても、「伝え方」と「伝える場面」の配慮が不可欠です。
周りを支える:ハラスメントを見かけたときにできること
ハラスメントの問題において、当事者だけでなく「周囲の人の対応」も非常に重要です。
被害者は孤立しやすく、助けを求めるのが難しい状況に置かれていることが多いため、周囲の気づきや行動が救いになるケースは少なくありません。「見て見ぬふり」を避け、傍観者ではなく“支援者”になるために、私たち一人ひとりができることを考えてみましょう。
まず話を「聴く」姿勢を持つ
誰かがハラスメントを受けていると感じたとき、まずは「相手の話をしっかり聴くこと」が大切です。大げさなアドバイスや解決策を急ぐのではなく、相手の感情や経験を否定せずに受け止める姿勢が求められます。
傾聴のポイント
- 相手のペースに合わせて話を聞く
- 「つらかったね」「話してくれてありがとう」と共感を示す
- 否定せず、判断を保留する
このような対応をするだけでも、被害者は「味方がいる」と感じ、心理的に大きな支えとなります。
必要であれば相談窓口を案内する
被害者が相談に踏み切れずにいる場合には、適切な相談窓口を案内することも有効です。自分が解決できなくても、信頼できる支援ルートをつなげるだけで大きな助けになります。
案内できる相談先の例
- 職場内のハラスメント相談窓口
- 労働局の総合労働相談コーナー
- 自治体やNPOの無料相談窓口
- 医療機関やカウンセラー
「こういうところがあるよ」「一緒に行こうか?」と声をかけることで、被害者が一歩を踏み出しやすくなるでしょう。
すぐに行動できなくても、記録や証言で支える
状況によっては、その場ですぐに介入できないこともあるでしょう。しかし、「何もできない」と諦めずに、できる範囲で被害者を支えることが重要です。その一つが、客観的な証言や記録を残すことです。
具体的なサポート方法
- 発言内容や日時、場所をメモしておく
- 他の目撃者とも情報を共有しておく
- 被害者が訴えたときに証言する用意をしておく
このような記録は、後に被害者が相談や調査に進む際の貴重な証拠となり、心強い味方になります。
周囲のちょっとした気づきや声かけが、被害者の「救い」となることは決して少なくありません。誰かを守る行動は、大きな勇気ではなく、小さな共感と配慮から始まることを覚えておいてください。
「ハラスメントではないけど、職場の雰囲気が悪い……」と感じる場合もあるでしょう。下記コラム記事で、職場の人間関係が悪い場合の対応方法をご紹介していますので、ぜひ併せてご一読ください。
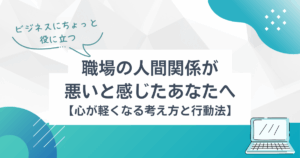
まとめ:自分にも、周りにもやさしい日常へ
ハラスメントを防ぐというと、堅苦しく難しいことのように感じるかもしれません。
しかし本質は、「お互いを思いやる関係づくり」にほかなりません。自分がどう行動するか、周りにどう寄り添うか。それらの積み重ねが、誰もが安心して過ごせる環境をつくる第一歩になります。
人間関係の信頼に基づく職場文化づくり
ハラスメントのない環境は、一人ひとりの努力だけでなく、組織全体の「空気感」や「文化」づくりとも密接に関係しています。
- 日頃から感謝や敬意を言葉にする
- 意見の違いを受け入れる土壌をつくる
- ミスに対して責めず、支え合う姿勢を示す
こうした積み重ねによって、職場やチームの中に「誰もが安心して声を上げられる空気」が生まれます。ハラスメントが起きにくい環境とは、信頼に支えられたコミュニケーションが活発な場所なのです。
自分ができる範囲で「変わる」意志を持つ
「自分には関係ない」「自分は被害者でも加害者でもない」と思っている人も多いかもしれません。しかし、ハラスメントは誰もが加害者にも被害者にも、そして傍観者にもなり得る問題です。
だからこそ大切なのは、「自分にできることを1つでも始めてみる」こと。
- 自分の言動を振り返る
- 困っている人に声をかける
- 違和感を無視せず、行動を起こす
それらの小さな行動が、周囲に影響を与え、組織をハラスメントのない良い方向性へ変えていけるのではないでしょうか。