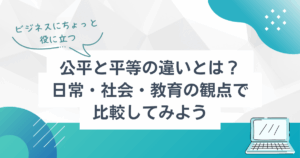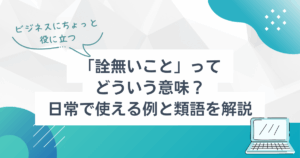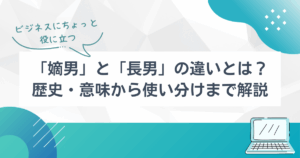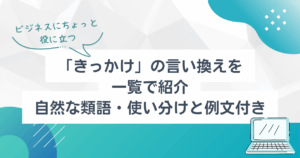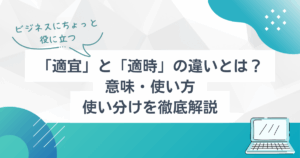退職2ヶ月前の申し出は非常識?やってはいけない退職と円満退職のコツ
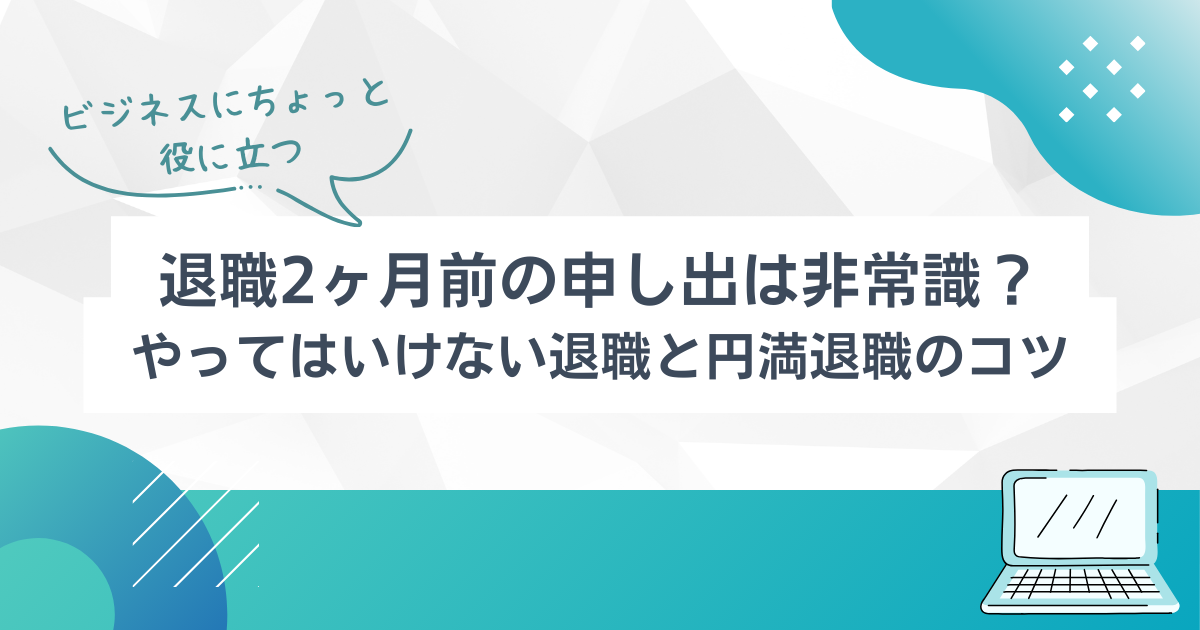
「そろそろ退職を考えているけれど、申し出るタイミングはいつがベストなのか…?」——退職を決意したとき、多くの人が悩むのがこの“申し出のタイミング”ではないでしょうか。中でも「退職の2ヶ月前」に伝えるのは非常識なのか、それとも適切なのか、職場との関係や就業規則によって判断が分かれるところでしょう。
本記事では、退職を伝える最適な時期とその理由、やってはいけないNG退職、そして円満に職場を離れるための具体的なコツについて詳しく解説します。これから退職を考えている方が、スムーズかつ後悔のない形で新しい一歩を踏み出せるよう、実務的かつ実践的な視点でお届けします。
退職時に「やってはいけないこと」とは?
退職は人生の転機のひとつ。
しかし、その去り際を誤ると、これまで築いてきた人間関係や信頼を一瞬で失ってしまうこともあります。ここでは、退職時に絶対に避けたい「やってはいけないこと」を具体例とともに紹介します。転職先にも響く可能性があるため、注意が必要です。
退職の連絡をせずに勝手に辞める(バックれる/飛ぶ)
退職の意志を伝えずに急に出社しなくなる、いわゆる「バックれる」や「飛ぶ」といった行為は、社会人として最も避けるべき非常識な行動です。
- 服務規律違反となる可能性が高い
- 残された同僚に多大な負担がかかる
- 今後のキャリアに悪影響を及ぼすことも(紹介やリファレンスに響く)
どんなに職場環境に不満があったとしても、最低限の手続きとマナーを守ることが、社会人としての責任ではないでしょうか。
同僚や部下を介した退職の意思伝達
直属の上司ではなく、仲の良い同僚や部下を通じて退職の意向を伝えるのも、トラブルの要因になります。
- 伝言ミスによるトラブルのリスクがある
- 上司との信頼関係を損ねる可能性が高い
退職は個人の自由ですが、あくまでビジネス上の手続きであることを忘れてはいけません。まずは直属の上司に、直接かつ冷静に伝えてはいかがでしょうか。
感情的・ネガティブな退職理由を口にする(不平・不満)
退職理由を聞かれた際に、職場への不満や人間関係のトラブルを感情的にぶつけるのはNGです。
- 職場に「後味の悪さ」を残してしまう
- 感情的な発言が噂として広まる可能性も
たとえ本音であっても、退職の場面では冷静さと配慮が求められます。ポジティブな言い回しに変換することで、円満な退職につながりやすくなるでしょう。
「円満退職」を目指すにはどうすればいい?
退職の理由がどんなに前向きなものであっても、伝え方や行動次第ではトラブルに発展することもあります。だからこそ、周囲と良好な関係を保ったまま職場を離れる「円満退職」は、社会人にとって大切なマナーのひとつです。ここでは、円満退職を実現するための基本ステップを紹介します。
まずは直属の上司に、丁寧に直接伝える
退職の第一報は、必ず直属の上司に対して直接行うのが基本です。メールやチャットではなく、対面やオンライン会議など“顔を合わせて”伝える姿勢が重要となります。
退職を伝えるコツ
- 退職を決意した理由を簡潔に伝える
- 業務に支障が出ない時期を考慮して申し出る
- 感情的にならず、冷静かつ丁寧な言葉遣いを心がける
こうした配慮ある対応が、上司からの信頼を最後まで損なわないコツと言えるでしょう。
退職理由はポジティブに、感謝も忘れずに
退職理由を伝える際は、なるべく前向きな表現に変換するのがポイントです。たとえば「人間関係がつらい」ではなく「自分を成長させる新たな環境に挑戦したい」といった表現が好まれます。
- 「〇〇の経験を活かして、新たなフィールドに挑戦したい」
- 「自社での経験があったからこそ、今の決断に至れた」
このように、これまでの職場への感謝の気持ちを示すことで、退職後の人間関係にも良い影響を与えられるはずです。
引き継ぎ内容を整理し、引き継ぎ計画を提示する
円満退職の鍵は、「自分の後任が困らないように準備すること」にあります。退職を伝えた後は、早めに引き継ぎ資料を作成し、周囲と共有しましょう。
- 自分が担当している業務一覧を洗い出す
- 進行中のプロジェクトや顧客対応の状況を記録する
- 引き継ぎスケジュールと対応者を明確にする
こうした準備をしっかり行うことで、周囲から「最後まで責任感を持っていた」と高く評価されることが多いです。
2ヶ月前に退職を伝えるのは非常識なのか?法的観点やマナーの観点
「退職の申し出は何ヶ月前が妥当なのか?」という疑問は、誰もが一度は抱くものです。結論から言えば、2ヶ月前の申し出は非常識ではなく、むしろ“理想的なタイミング”と言えるでしょう。
ここでは、法的根拠とビジネスマナーの両面から、その理由について解説いたします。
前提:民法では「2週間前」で退職可能と定められている
民法第627条では、期間の定めのない雇用契約(例:正社員)においては「退職の意思を2週間前に申し出れば、いつでも退職が可能」とされています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:e-Gov「民法(明治二十九年法律第八十九号)」より
簡単に整理すると、正社員の場合には
- 退職の意思表示はいつでもできる
- 意思表示から2週間後に退職ができる
- 会社の同意がなくても法律上は有効
上記のような意味となります。
それでも「2ヶ月前に伝えるのはむしろマナー」とされる理由
実務の現場では、「1~2ヶ月前に伝えるのが妥当」とされることが一般的です。その背景には、以下のような事情があります。
退職の連絡を「2ヶ月前」にするメリット
- 業務の引き継ぎに十分な期間を確保できる
- 後任者の採用・育成に余裕が生まれる
- 繁忙期やプロジェクト進行状況への影響を最小限にできる
このように、2ヶ月前の申し出は職場への配慮として高く評価される傾向があり、むしろ「円満退職のためのベストな選択肢」と言えるでしょう。
職場の状況や上司の反応も理解して準備を
2ヶ月前に退職を伝える場合でも、ただ伝えればいいというわけではありません。職場ごとの事情や上司の性格、チーム体制などを把握したうえで、慎重に進めることが大切です。
- 繁忙期やプロジェクトの山場を避ける
- 上司のスケジュールを確認し、落ち着いた場面で話す
- 感情的な反応にも冷静に対応できるよう心構えをしておく
「自分の都合」だけでなく、「相手の都合」も考慮することで、退職がスムーズに進むだけでなく、最後まで信頼される人材として職場を後にできるでしょう。
退職でありがちなトラブルと回避策
退職は単なる手続きではなく、人間関係や社内ルールが絡む“繊細なイベント”でもあります。スムーズに辞めたいと思っていても、思わぬトラブルに直面することも少なくありません。
ここでは、退職時によくある問題と、その対処法を具体的に解説します。
就業規則が「1〜3ヶ月前通知」を求めているケースへの対応
企業の就業規則には、「退職は1ヶ月前までに申し出ること」「3ヶ月前通知が必要」といった規定がある場合があります。これに気づかず退職を進めると、思わぬトラブルになることも。
- まずは自社の就業規則や雇用契約書を確認する
- 書面上での規定がある場合は、それに従うのが基本
- どうしても早く退職したい場合は、上司と率直に相談し、協議する姿勢を見せる
就業規則に縛られるのが不当と思える場合でも、法的なアプローチではなく、まずは「対話」で解決を図るのが円満な方法と言えるでしょう。
上司が引き止めてくる理由と、冷静に対応する方法
退職の申し出に対し、上司が強く引き止めてくるケースも少なくありません。その背景には、以下のような事情があります。
- 業務の穴埋めがすぐにできない
- 部署の人員計画に影響する
- 離職率が人事評価に影響する上司もいる
引き止められた際は、感情的にならず、丁寧に「決意は固い」旨を伝えましょう。
- 「自分なりに熟慮した上での決断です」と伝える
- 可能であれば、今後のキャリアビジョンを添える
- 感謝の気持ちを忘れず、誠実に対応する
話し合いが平行線になる場合でも、相手の立場を理解した上で対応することで、関係を悪化させずに済むでしょう。
離職に向けたフォロー・退職後の関係を良好に保つポイント
退職が決まった後も、「辞めるから関係ない」という姿勢は避けるべきです。むしろ、最後の立ち振る舞いがその人の印象を決定づける重要な期間です。
- 引き継ぎを丁寧に行い、業務マニュアルなども整備する
- 社内への報告タイミングを上司と相談し、混乱を避ける
- 退職後も連絡が必要な業務がある場合は、連絡方法を明確にしておく
また、最終出勤日や送別会などのタイミングで、これまでの感謝を伝えることで、退職後も良好な関係を保ちやすくなります。元職場との縁が、将来のチャンスにつながることもあるのです。
退職に関するよくある疑問をFAQ形式で紹介
退職を決意してから実行に移すまでの間、多くの人がさまざまな疑問や不安を抱えます。ここでは、退職に関する“よくある質問”に対して、実務的かつマナーに配慮した回答をお届けします。
退職の2ヶ月前に伝えるのは本当に非常識ですか?
いいえ、むしろ理想的なタイミングといえます。
法律上は2週間前でも問題ありませんが、職場の業務引き継ぎや人員体制を考えると、1〜2ヶ月前の申し出は「配慮ある行動」として評価される傾向にあります。
民法では2週間前でいいのに、会社規則が1ヶ月前なのはなぜ?
組織運営上の必要性から、会社ごとのルールとして定めているためです。
民法はあくまで最低限のルール。円滑な業務引き継ぎや人員調整のため、会社側が独自に「1ヶ月前の退職申し出」や「二ヶ月前の退職申し出」などの規定を設けるのは一般的です。
上司が感情的に引き止めてくるとき、どう対応すべき?
感情に流されず、冷静かつ誠実に対応しましょう。
「熟慮した上での決断であること」「感謝していること」をしっかり伝えましょう。感情的にならず、あくまで“社会人としての節度ある対話”を心がけることが大切です。
退職理由は正直に言わないとダメですか?
感情に流されず、冷静かつ誠実に対応しましょう。
「熟慮した上での決断であること」「感謝していること」をしっかり伝えましょう。感情的にならず、あくまで“社会人としての節度ある対話”を心がけることが大切です。
有給休暇を消化するのは非常識に見えますか?
法的にもマナー的にも、有給消化は正当な権利です。
ただし、「引き継ぎが不十分」「繁忙期に丸ごと休む」といった形ではトラブルの元になります。上司と調整し、業務に支障が出ないよう計画的に取得しましょう。
有給休暇を全て消化してから退職する場合には、引き継ぎを考慮して退職日を決めてはいかがでしょうか。
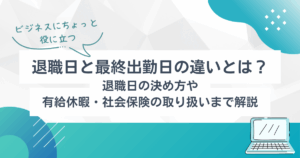
同僚にはいつ、どう伝えるのがベストですか?
上司からの了承を得た後、適切なタイミングで伝えるのがマナーです。
「突然の退職報告」は周囲を驚かせるため、上司と相談して社内周知のタイミングを合わせましょう。できれば、感謝の言葉を添えて前向きなトーンで伝えると印象が良くなります。
退職届と退職願の違いとは?どちらを出すべき?
職願」は申し出、「退職届」は意思の確定通知です。
- 退職願:退職の意思を“伺う”段階(上司の了承前に提出)
- 退職届:退職日が確定した後に提出する“最終通知”
多くの企業では、まず口頭で意思を伝え、了承後に「退職届」を提出する流れが一般的です。

引き継ぎが終わらない場合、退職は延期すべきですか?
原則として、退職の決定を延期する必要はありません。
ただし、自分ができる範囲での引き継ぎは誠実に行うべきです。業務マニュアルの作成や引き継ぎ会議の実施など、計画的に進めておけば問題視されることは少ないでしょう。
まとめ:2ヶ月前の退職申し出は非常識ではなく「誠実な配慮」
退職は、人生の転機であると同時に、職場との最後の関わりでもあります。2ヶ月前に退職を申し出ることは、法律上は義務ではないものの、引き継ぎや業務調整の観点から見ても非常に“誠実な行動”と言えるでしょう。
どんなに素晴らしい転職先が決まっていたとしても、今いる職場を円満に去ることは、未来の自分の信用にもつながります。感謝と配慮を忘れず、誠実な退職を推奨いたします。