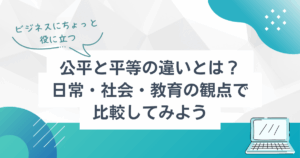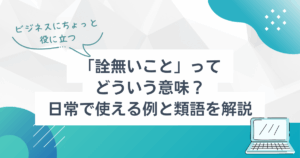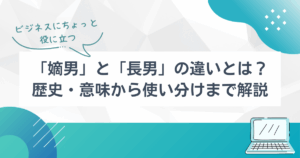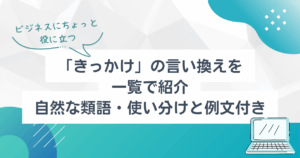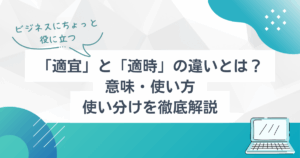「有給のない会社」は違法?有給が取れない・ないと言われたときの対応方法や相談先

「うちは有給がないから」「忙しいから有給は取れない」――そんな職場で働いていませんか?
本来、有給休暇は労働者の正当な権利であり、一定の条件を満たせば必ず取得できるものです。しかし、会社側の誤解や意図的な対応により、労働者が有給を使えずにいるケースも少なくありません。
本記事では、「有給のない会社」は違法なのかという点から、有給が取れない場合の具体的な対処法、そして相談できる機関についてまで、わかりやすく解説します。労働者としての権利を正しく理解し、健全な職場環境を守るための第一歩を踏み出しましょう!
有給のない会社とは?法律上はあり得ない!
「うちの会社には有給休暇がない」と言われた経験はありませんか?
実はこれは、労働基準法に照らし合わせると非常に問題のある発言です。有給休暇はすべての労働者に対して法律で保障された権利であり、原則として「有給がない会社」は法律上認められていません。
有給休暇は法律で定められた労働者の権利
労働基準法第39条では、一定の条件を満たした労働者に対して、年次有給休暇を付与することが義務づけられています。
(年次有給休暇)第三十九条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用元:e-Gov「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」より
わかりやすく、有給休暇が発生する条件を整理すると、
- 雇い入れの日から6か月継続勤務している
- その期間の出勤率が8割以上である
この条件を満たした労働者に対して、有給休暇を取得する権利が発生します。これは、雇用形態にかかわらず、正社員はもちろん、パートやアルバイトも対象です。
つまり、「正社員じゃないから有給はない」「うちは小さい会社だから」などの理由で有給休暇を与えないのは、法律違反にあたる可能性が高いといえるでしょう。
ただし、パートタイムや週の勤務日数が少ない労働者については、「所定労働日数」「週所定労働時間」に応じて比例付与される仕組みがあり、付与される日数が正社員より少なくなるケースもあります。この日数は法律で明確に定められており、勤務日数や勤続年数に応じて計算されます。
「有給がない」と言われた場合でも違法なケースが多い【(例外あり】
会社から「有給制度はない」と告げられても、実際には労働者に発生している有給を使わせていないだけというケースが見られることがあります。こうした対応は、以下のような法律違反に該当する可能性があります。
- 有給休暇の付与義務違反
- 申請した有給を正当な理由なく拒否する不当な運用
- 有給を取得すると評価が下がるなど、事実上の取得妨害
ただし、例外的に有給休暇が発生しないケースもあります。たとえば、短期の雇用契約で6か月未満の勤務しかしていない場合や、出勤率が極端に低い場合などが該当します。
それでも、「全員に有給はない」「会社の方針で有給は存在しない」といった対応は、原則として違法性が高いため注意が必要です。
有給が「本当にない」ケースはどんなとき?
原則として、有給休暇は法律で認められた権利ですが、すべての労働者に自動的に発生するわけではありません。
条件を満たしていない場合には、有給が「本当にない」こともあります。ここでは、正当な理由で有給休暇が付与されないケースを具体的に見ていきましょう。
入社から6ヶ月未満・出勤率が8割未満の場合
有給休暇が付与されるためには、「継続勤務6ヶ月以上」かつ「出勤率8割以上」という2つの条件を満たす必要があります。
入社から6ヶ月未満・出勤率が8割未満の場合は有給休暇が付与されない
- 継続勤務6ヶ月未満
- 入社してから6ヶ月が経過していない場合、有給休暇の権利はまだ発生していません。
- 出勤率8割未満
- 6ヶ月以上勤務していても、体調不良や私用などで欠勤が多く、出勤率が80%未満であった場合も有給は付与されません。
これらの条件は明確に法律で定められているため、企業が有給を付与しない正当な理由となり得ます。
業務委託・請負契約など、雇用契約ではない働き方
有給休暇の対象となるのは「労働者」に限られます。
業務委託契約や請負契約といった形で働いている場合、雇用契約が存在しないため、労働基準法の適用外となります。
例えば、
- フリーランスとして個人事業主契約をしている
- 企業と請負契約を結んで働いている
- プロジェクト単位での委託業務のみ行っている
こうした働き方では、有給休暇の権利は発生しません。
ただし、契約書で独自に「休暇」や「報酬の保証」が定められている場合は別ですので、契約内容をよく確認しましょう。
年間の勤務日数が48日未満など短すぎる場合
パートやアルバイトなどの短時間勤務者においても、勤務日数が極端に少ないと、有給休暇が発生しないケースがあります。
たとえば、1年間の勤務日数が48日未満(週1回以下)であれば、有給付与の対象外となります。
これは、「所定労働日数に応じた比例付与」の制度によるもので、勤務日数が少ないほど有給の付与日数も減少し、一定以下になると付与されなくなるという仕組みです。
このように、有給が「本当にない」ケースは例外的ではありますが、確かに存在します。ただし、それが適用されるのは特定の条件下のみであり、「一律で有給が存在しない」という企業の主張は、ほとんどの場合において不当といえるでしょう。
「有給のない会社」で働くリスクとは?
「うちは有給がないから」と言われたまま働き続けると、企業側・労働者側の双方にさまざまなリスクが生じます。
これは単なる制度の問題ではなく、職場環境の健全性や法令順守の姿勢、さらには労働者の健康や将来にも直結する重大な問題です。以下では、その具体的なリスクについて解説します。
法律違反となるリスクと罰則
労働基準法に違反して有給休暇を与えない企業には、法的な罰則が科される可能性があります。
具体的には、
- 労働基準法第39条違反:有給休暇の付与義務に違反
- 罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第120条)
厚生労働省や労働基準監督署による調査・是正勧告の対象にもなり得るため、企業にとっては信用失墜だけでなく、行政処分を受けるリスクもあるのです。

社会的信用の低下や「ブラック企業」認定されるリスク
有給制度の未整備や取得の妨害は、「労働者の権利を軽視する企業」としての評価につながりかねません。実際に、以下のような事態が想定されます。
- SNSでの内部告発・悪評拡散
- 転職サイトで「ブラック企業」として口コミが広がる
こうした情報が広まれば、優秀な人材の採用が難しくなり、社内外の信用が大きく揺らぐでしょう。
心身への影響や離職率の上昇といった労働者への負荷
有給休暇が取れない環境で働き続けると、労働者は心身ともに大きな負担を抱えることになります。
たとえば、
- 慢性的な疲労やストレスによる体調不良
- モチベーションの低下によるパフォーマンスの悪化
- 仕事とプライベートの両立が困難に
こうした状況が続けば、結果として離職率の増加にもつながり、企業の生産性や職場環境にも悪影響を及ぼします。
有給休暇の未整備は、単なる制度上の問題にとどまらず、企業経営や従業員の人生そのものに深く関わるリスクを内包しているのです。
実際に「有給がない」と言われたらどうすべきか?
「うちは有給がない」と会社に言われたとき、そのまま黙って受け入れてしまうのは危険です。
多くの場合、それは違法な対応であり、声を上げなければ状況は改善されません。ここでは、労働者が取るべき具体的な対応策を段階的に解説します。
上司・人事や相談窓口にまずは相談
まずは冷静に、司や人事担当者に「有給休暇は労働基準法で定められていること」「自分に取得の権利があると考えていること」を伝えましょう。その際には以下のような準備が効果的です。
上司や人事に相談する前に確認しておきたい事項
- 就業規則や雇用契約書を確認する
- 自身の勤続期間や出勤率を把握する
- 証拠となる会話ややり取りを記録する(メール・メモなど)
社内に相談窓口やコンプライアンス部署がある場合は、そこへ直接訴えるのも有効です。
企業によっては制度の誤解や運用ミスによる対応の場合もあるため、まずは内部での解決を試みるのが基本です。
内部で解決できないときは労働基準監督署に相談
会社側が話し合いに応じなかったり、改善の意思が見られない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。労基署は労働基準法違反の疑いがある事案を調査・指導する公的機関です。
- 匿名での相談も可能
- 必要に応じて是正勧告が行われる
- 相談は無料で利用可能
最寄りの労基署に出向くか、厚生労働省の公式サイトから問い合わせることで、状況に応じたアドバイスを受けることができます。

退職時の有給消化や弁護士など専門家の活用
もし改善が見込めず、最終的に退職を選ぶ場合には、退職時の有給休暇の消化を忘れずに行いましょう。
有給は使用の意思を示すだけで取得できる「時季指定権」が労働者側にあるため、会社の許可がなくても原則として取得可能です。
また、以下のような状況では弁護士や労働問題に詳しい専門家に相談するのも有効です。
- 有給を理由に不利益な扱いを受けた
- 賃金未払い・退職妨害なども併発している
- 精神的・身体的な被害が大きい
法的対応を視野に入れることで、自分の権利を守ると同時に、同じような被害を防ぐための一歩にもなります。

有給取得がしづらい職場の問題点とは?
有給休暇が制度として存在していても、実際には取得しづらい――そんな職場は少なくありません。形式上は合法でも、実質的に有給取得を阻む文化やルールがある場合、それは「隠れブラック企業」とも言える環境です。ここでは、有給取得がしづらい職場に共通する問題点を整理して解説します。
「誰も休まない文化」「属人化された業務」
職場全体に「誰も有給を取らない」雰囲気があると、新入社員や若手が休みを申請することに大きな抵抗を感じます。特に以下のような文化や体制は、有給取得を難しくします。
- 「上司すら休まない」という暗黙の圧力
- 特定の人に業務が集中しており、代替が効かない
- 人手不足で休める余裕がない
業務の属人化が進んでいると、その人が休むことで仕事が止まってしまうため、職場全体で「休めない」空気が生まれやすいのです。これは組織のマネジメントの問題でもあり、長期的には企業の生産性低下を招きかねません。
取得理由を制限する「社内ルール」による阻害
法律上、有給休暇を取得する際に理由を伝える義務はありません。にもかかわらず、社内で「病気や冠婚葬祭以外は不可」「理由が正当でないと認めない」などの独自ルールを課している場合、それは違法性が高い運用といえます。
このような職場では以下の問題が生じます。
- プライベートの予定が理由だと却下される
- 上司の主観で可否が決まる
- そもそも申請自体がしづらい雰囲気になる
労働者の「時季指定権」を不当に制限することは、労働基準法に反する可能性があるため、慎重な対応が必要です。
罪悪感や同調圧力による心理的ハードル
制度的には取得可能であっても、職場内の人間関係や雰囲気によって心理的に「取りづらい」と感じるケースも多くあります。
具体的には、
- 「みんな忙しいのに自分だけ休むのは気が引ける」
- 「申し訳なさそうに言わないと角が立つ」
- 「評価が下がるのでは」と不安になる
こうした同調圧力は、メンタルヘルスの悪化やモチベーションの低下にもつながります。有給取得を当たり前にするためには、制度だけでなく「文化の是正」も求められるのです。
改善の流れと有給取得が当たり前の職場文化へ
近年、労働環境の見直しが進み、「有給休暇の取得を当たり前にすること」が社会全体の課題として認識されるようになってきました。企業もただ制度を用意するだけでなく、積極的にその運用を促し、働きやすい職場づくりを目指す必要があります。ここでは、有給取得促進のための法制度や考え方、そして企業にとってのメリットを解説します。
働き方改革:有給取得の「義務化」(年5日以上取得)
2019年4月から施行された「働き方改革関連法」により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年5日以上の有給を企業が確実に取得させることが義務化されました。これに違反した企業には罰則も設けられています。
- 対象:年次有給休暇が10日以上ある労働者
- 義務:最低年5日、有給を取得させる(企業の責任)
- 罰則:労働基準法違反として、30万円以下の罰金
この制度により、「制度はあるが使われない」状態から、「実際に使わせる」段階へと法的にも進展しました。

取得ルール(時季変更権、計画的付与、時間単位付与)の理解
有給取得には一定のルールがありますが、それを正しく理解・活用することで、より柔軟な働き方が可能になります。
- 時季変更権:会社は業務に重大な支障がある場合、有給の時期を変更することが可能
- 計画的付与:労使協定により、一定の日に全員の有給を計画的に取得させる制度(夏季休暇など)
- 時間単位付与:年5日を超える有給については、時間単位での取得も可能(育児・通院などに活用)
これらの仕組みを活かすことで、業務に支障を与えることなく、労働者のライフスタイルに合わせた柔軟な休暇取得が実現します。

有給取得が企業にもたらすメリット(生産性・健康・採用)
有給取得を推進することは、企業にとっても多くのメリットがあります。単なる「コスト」ではなく、投資としての効果があると捉えるべきでしょう。
- 生産性向上:しっかり休むことで集中力や仕事の質が向上
- 健康維持:メンタルヘルスや身体の健康維持に寄与
- 採用力の強化:働きやすい企業というイメージが定着し、優秀な人材を確保しやすくなる
つまり、有給休暇の取得促進は「働きやすさ」だけでなく、「企業の競争力向上」にも直結する重要な要素なのです。
まとめ:有給休暇は「制度」ではなく「当然の権利」
有給休暇は、労働者が安心して働き続けるために不可欠な権利であり、法律でも明確に保障されています。「有給がない」「使えない」という職場には、法的リスクや文化的課題が潜んでいる可能性が高く、早期の対処が求められます。
万が一、有給を拒否された場合でも、上司や人事への相談、労基署や専門家への相談など、労働者が取れる手段は多数あります。また、有給取得は企業側にとっても、生産性や採用力の向上といったメリットがあるため、積極的に推進すべき課題です。
働く人が安心して休めること――それが当たり前となる職場づくりこそ、真に健全な労働環境への第一歩です。自分の権利を正しく理解し、必要なときにしっかりと活用していきましょう。